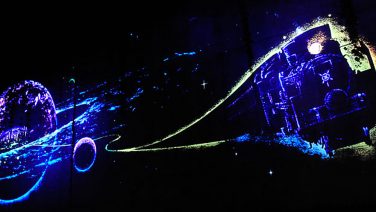 宮沢賢治の周辺
宮沢賢治の周辺 宮沢賢治の周辺(9)
第9話 「慈悲」について② 一口に仏教といっても、現在のタイやミャンマー、ラオス、カンボジアのような国々で信仰されているものと、中国経由で日本に入ってきた、いわゆる大乗仏教といわれるものとでは、中身がずいぶん異なるようである。釈迦牟尼ことゴ...
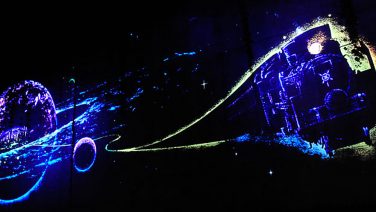 宮沢賢治の周辺
宮沢賢治の周辺 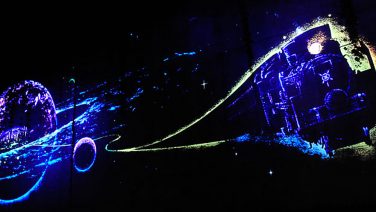 宮沢賢治の周辺
宮沢賢治の周辺  宮沢賢治の周辺
宮沢賢治の周辺  Senior Moter Drive
Senior Moter Drive  Senior Moter Drive
Senior Moter Drive  Senior Moter Drive
Senior Moter Drive  宮沢賢治の周辺
宮沢賢治の周辺  宮沢賢治の周辺
宮沢賢治の周辺 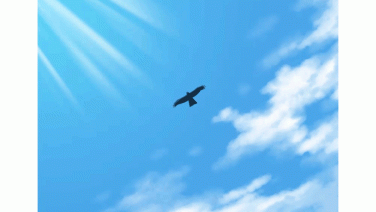 論文
論文  Senior Moter Drive
Senior Moter Drive  宮沢賢治の周辺
宮沢賢治の周辺  Senior Moter Drive
Senior Moter Drive  宮沢賢治の周辺
宮沢賢治の周辺  Senior Moter Drive
Senior Moter Drive  宮沢賢治の周辺
宮沢賢治の周辺  Senior Moter Drive
Senior Moter Drive  宮沢賢治の周辺
宮沢賢治の周辺 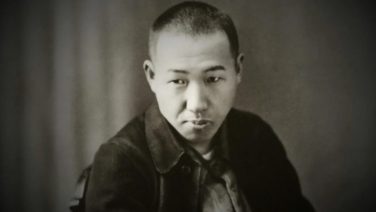 宮沢賢治の周辺
宮沢賢治の周辺  Senior Moter Drive
Senior Moter Drive 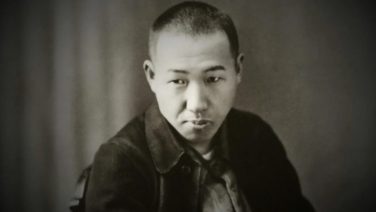 宮沢賢治の周辺
宮沢賢治の周辺  Senior Moter Drive
Senior Moter Drive  創作
創作  小説のために
小説のために  創作
創作  創作
創作  創作
創作  小説のために
小説のために  小説のために
小説のために 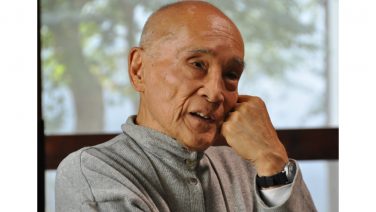 小説のために
小説のために 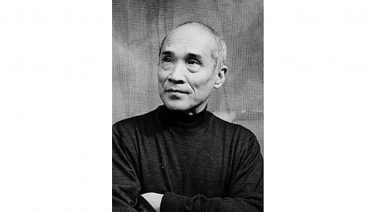 小説のために
小説のために  創作
創作  創作
創作  創作
創作  創作
創作  創作
創作  創作
創作  創作
創作  創作
創作  創作
創作  創作
創作