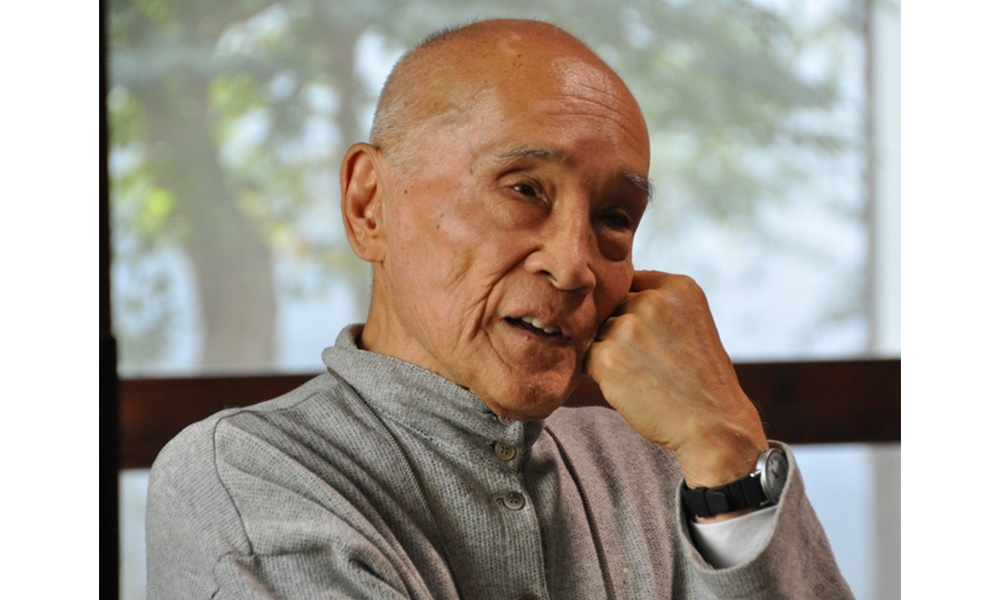3
谷川俊太郎の詩を読んで感じるのは、ひとことで言うと「嘘くさくない」ということだ。賢しらさを感じさせないというか、殊更に作りましたという痕跡が希薄である。たしかに作ってはいるのだけれど作為を感じさせない。言葉が自然に生まれているような感じを与える。そういうところはモーツァルトの音楽にちょっと似ているかもしれない。
別の言い方をすると、言葉と作者のあいだに隙間がない。作者の感覚や知覚から、直に言葉が生まれているように見える。作者は詩の言葉の場所にいつもいて、そこを生きているということが自然に伝わってくる。このことは谷川俊太郎の詩の大きな特徴だと思う。
三年ほど一緒に連続討議をやっている森崎茂さんは、最近のブログのなかでつぎのように書いている。
生の原像はだれのなかにも内挿されている。わたしの内包表現論は生をまるごと表現にしようとしている。観察する理性は表現の主体と表現を分離する。俯瞰による観察する理性は、それがどんなイデオロギーであれ、知識人と大衆という権力による分割を行使する。生活と表現の分離だ。(「歩く浄土」135)
ここで言われていることは、そのまま谷川俊太郎の詩に当てはまる。森崎さんは「喰い、寝て、念ずる」ことが「生の原像」だと言う。誰もが普通にやっていることだ。これをまるごと表現にする。表現でありうるという確信の場所から、森崎さんの内包表現論は出発している。
谷川俊太郎の詩も同じ場所から、すなわちどんなものでも(「うんこ」でさえも)詩になりうるというところから出発している。それは森崎さんの言葉で言えば、「喰い、寝て、念ずる」という生の原像をまるごと詩にしてしまうということだ。どうやって? 俯瞰する視線でも観察する理性でもない、「ポエムアイ」という新しい眼差しをつくり出すことによって。森崎さんなら「内包的な眼差し」と言うだろう。すべてのものを詩(表現)として見る眼差し。このとき生活は表現と分離できないものになる。詩人が一緒に暮らしている現実の妻は、彼の詩において表現された「妻」と等価である。
おそらく谷川俊太郎は書かれた詩だけを詩とは考えていないし、詩人を特別な存在とも考えていない。なぜなら彼にとって詩は、「喰い、寝て、念ずる」という場所で生まれるものであり、こうした「生の原像はだれのなかにも内挿されている」からである。したがって詩も、詩を書くことも、なんら特権的なものではない。そのようなもので詩はありえるはずがない。詩人が読者にたいして行使する権力について、この詩人はとても敏感だ。
何ひとつ書く事はない
私の肉体は陽にさらされている
私の妻は美しい
私の子供たちは健康だ
本当の事を言おうか
詩人のふりはしてるが
私は詩人ではない
(「鳥羽」1 部分)
1965年に発表されているから、作者は34歳である。34歳のごくありきたりな夫、一人の父親という場所で言葉が紡がれている。だから「私の妻は美しい」という一節に嫌味は感じられず、「詩人のふりはしてるが/私は詩人ではない」という述懐にも衒いがない。作者の自然な表白として読める。さらに言えば、高度経済成長期にあった健康な戦後日本の空気が、この詩には充溢している。それは紛れもなく、作者が一人の生活者として吸っていたと信じられるものだ。
もう少し批評的な言い方をすると、谷川俊太郎の詩は概して自己表現っぽくないのだ。一人の作者の「自己」を表現したものというよりは、みんなが共感できる言葉の場所を生きようとしている詩というふうに読める。まず難しい言葉が一つも使われていない。誰にもわかる言葉、誰でも使うことのできる言葉だけで書かれている。谷川俊太郎の作品が多くの読者やファンを獲得している理由は、そのあたりにあるのかもしれない。いわゆる「自己表現」によっては人と人はつながらないということを、おそらく本能的に知っているのだろう。それ以前に、文学者や詩人の「自己」なるものが信じられていない。だから彼の詩は、とても風通しがいい。その詩や言葉に触れると、心が伸びやかになる。
谷川俊太郎の詩にはひらがな表記の詩や、子ども向けに書かれたものがたくさんあるけれど、多くは幼児にも大人にも伝わると思う。もちろん伝わり方や伝わっているものは違うだろうが、何か「いい感じのもの」が伝わっているはずだ。それは彼の詩が、一人の詩人や文学者の自己表現であることを放棄した場所から出発しているからだと思う。
はなのののはな
はなのななあに
なずななのはな
なもないのばな
(「ののはな」)
一見、他愛のないことばあそびのように見えるけれど、非常に高度でラディカルな詩だと思う。谷川俊太郎の膨大な詩業のなかでも、いちばん遠くまで行っている詩の一つかもしれない。
意味はほとんどない。音の心地よさだけで何かが伝わってくる。その「何か」は、おそらく言葉を知らない幼児にも、認知症の老人にも伝わるものだ。何か、やわらかくて、暖かくて、豊かで、楽しくリズミカルで、淀みなく流れていて、動いていて、飛び跳ねていて……そういう「いい感じのもの」が伝わるはずだ。この詩が音韻を研究し、緻密に計算されて成ったものかというと、ちょっと違う気がする。やはりモーツァルトの音楽のように、何気なく自然に出来上がっているように見える。
むしろ作者のほうが、音によって何かを伝えようとしていた時代、そうした言葉の古層へ赴いたと言ったほうがいいかもしれない。近代以前が意図されているわけだが、作者の意図は勢い余って中世も古代もすっ飛ばし、太古にまで届いてしまっている観がある。言葉が表記以前に音であった時代。ヒトが声を出すことで互いに応答し、その面白さに夢中になって、「ななななな」とか「ののののの」とかやって嬉しくてしょうがなかったころ。やがて音を選ぶことに意識的になり、「なのなの」とか音を組み合わせることを発見し、さらには「ば」とか「ぱ」とか濁音や破裂音にも目覚め、「ワォー、おれたちってなんかスゴイ」と思った、そういう場所に作者は降り立っているように見える。
このときぼくたちは、言葉の初源に立ち会っているのかもしれない。人間の言葉は、「いい感じのもの」を共有することによって生まれ、より多くの人と分かち合うために発達してきたのではないだろうか。(2017.2.19)