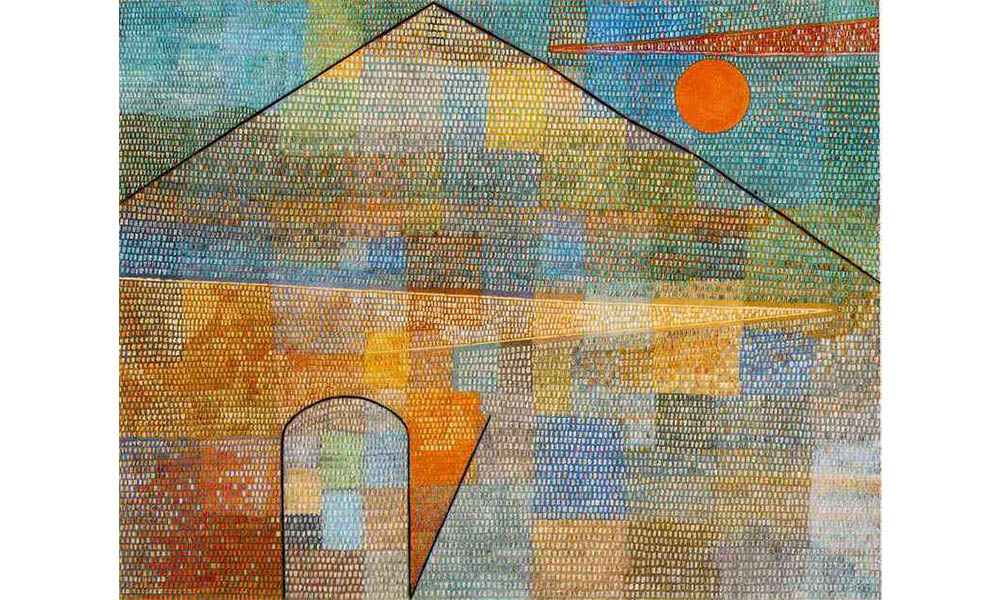4
谷川俊太郎の詩はおかしい。なんかヘンだ。どうしてこんなものができちゃったんだろう、と思わせる詩がある。作ったというよりはできちゃった。うっかりこの世に誕生してしまった。まるで詩人と言葉が一夜の過ちを犯したかのような、その副産物としての詩。
いるかいるか
いないかいるか
いないいないいるか
いつならいるか
よるならいるか
またきてみるか
いるかいないか
いないかいるか
いるかいるか
いっぱいいるか
ねているいるか
ゆめみているか
(「いるか」)
いったいどうなっちゃっているか。どうなっちゃってもいないかいるか。いけない、うつっちゃったいるか……というように、谷川俊太郎の詩は感染力が強い。楽しい気分が感染する。言葉って、こんなに楽しいものだったんだ!
おそらく誰よりも作者自身が、詩を作ることを楽しんでいるのだと思う。言葉と戯れるようにして詩を作る。その楽しさが伝わってくる。たんぽぽの綿毛のようにふわふわ風に乗って飛んでくる。難しいことをやっていると思わせない。知的だけれど知的な感じがしない。無知性なのではなく、知性の匂いをうまく消せている。
この「いるか」という詩にしても、ほとんど言葉の組み合わせだけでできている。だからつい、うつってしまうのだ。ぼくにもできそうな気がする。誰にもできそうな気がする。賢いAIが、「ドレ、オレモヒトツヤッテミヨウ」とか思いそうな気がする。まさに詩という表現様式のシンギュラリティ、言葉というビョーキのパンデミックだ。こういう詩を読んでいると、ほら、きみもこんなふうにして詩を作ればいいんだよ、と誘惑されている気分になる。何も特別なことじゃないんだよと。とはいっても、これだけの詩を誰もが簡単に作れるわけではない。でも、できそうな気がする。たくさん作っているうちに、うっかり偶然にできちゃいそうな気がする。詩を作ることを、谷川俊太郎はデジカメで写真を撮るように手軽なものにしてくれた。
頭で考えて作っている詩ではないのだろう。なんだか手仕事みたいにして出来上がっている気がする。愛用の万年筆で、「いるか、いるか、いないか、いるか」などと書いているうちに出来上がったような感じを受ける。手を使って紙に言葉を書いていく喜びが詩に溢れている。それが伝わってきて、詩に触れるぼくたちを幸せな気分にしてくれる。喜びを表現した詩はたくさんあるけれど、詩を作る喜びが伝わってくる詩って、あまりない気がする。というか、この詩人のもの以外にあるだろうか? きっと彼は木や石や土や布や紙などを扱う職人と同じレベルで、詩や言 葉というものをとらえているのだろう。
こんな空想がふくらんでくる。たとえば円空や木喰みたいな彫刻家というか作仏師が、仏像を彫るために手近な木材を探して山に入る。その木を持ち帰って仏像を彫る。何年も、何十年もやっているうち、山に転がっているなんの変哲もない自然木に神仏の姿を見ることができるようになる。手を加えてわざわざ彫らなくても、この雨に打たれ、日に焼かれた自然木こそ尊い神仏の姿そのままではないか、といった境地に引き込まれる。彼は木を工房に持ち帰ってつくづく眺め、「うん、これを彫る必要はない」とか「これ以上のものは彫れん」とか、一人で納得し酒を飲んで寝てしまう……ということを谷川俊太郎がやっているのかどうか知らないけれど、彼の詩って、草木国土悉皆成仏の本覚思想みたいなところがある。詩的な眼差しで見れば万物は仏性を有して成仏しておる、なんてね。
脱線ついでに円空の話をもう少しつづけよう。生涯に十二万体の仏像を彫ることを念願したと言われる円空は、きっと仕事も早かったのだろう。作仏師としての三十年の生涯に残した仏像は、円空仏と確認されているものだけで約五千体といから、相当のスピードで彫り上げていたことが想像される。その円空仏を見ると、自然木のもつ歪みや反りや節目、ひび割れなどをうまく利用したものが多いことに気がつく。木に力を加えて無理やり自分の作品にしてしまうのではなく、木の癖とか個性を生かし、それを取り込んで自然に作品が出来上がっている。
唐突に「性」と言ってしまいたくなるところだ。円空と木の関係は「性」ではないだろうか。谷川俊太郎が言うところの「ポエムアイ」。「もはや詩をこすりつける必要はどこにもなかった。」たしかに詩的な眼差しをもつことができれば、言葉をこねくりまわして詩にする必要はない。同じような眼差しで、円空は木を見ているのだと思う。その場で、そのものと取り結ぶ関係において見ている。一本一本の木を二人称で見ている。その表情によぎられて作品がやって来る。作品は円空のものでも自然木のものでもなく、人と木のあいだにある。この関係が「性」であり、「表現」とは本質的に「性」であると言っていいような気がする。
性としての表現、表現としての性。その見事な達成と思われる詩をあげてみる。ぼくのいちばん好きな谷川俊太郎の詩です。
ネロ
もうじき又夏がやってくる
お前の舌
お前の眼
お前の昼寝姿が
今はっきりと僕の前によみがえる
お前はたった二回程夏を知っただけだった
僕はもう十八回の夏を知っている
そして今僕は自分のや又自分のでないいろいろの夏を思い出している
メゾンラフィットの夏
淀の夏
ウイリアムスバーグ橋の夏
オランの夏
そして僕は考える
人間はいったいもう何回位の夏を知っているのだろうと
ネロ
もうじき又夏がやってくる
しかしそれはお前のいた夏ではない
又別の夏
全く別の夏なのだ
新しい夏がやってくる
そして新しいいろいろのことを僕は知ってゆく
美しいこと みにくいこと 僕を元気づけてくれるようなこと 僕をかなしくするようなこと
そして僕は質問する
いったい何だろう
いったい何故だろう
いったいどうするべきなのだろうと
ネロ
お前は死んだ
誰にも知られないようにひとりで遠くへ行って
お前の声
お前の感触
お前の気持ちまでもが
今はっきりと僕の前によみがえる
しかしネロ
もうじき又夏がやってくる
新しい無限に広い夏がやってくる
そして
僕はやっぱり歩いてゆくだろう
新しい夏をむかえ 秋をむかえ 冬をむかえ
春をむかえ 更に新しい夏を期待して
すべての新しいことを知るために
そして
すべての僕の質問に自ら答えるために
(「ネロ-愛された小さな犬に」)
この詩の心地よさを、どう言えばいいだろう。誰もが、この心地のいい詩の世界に入っていくことができる。この世界をともに生きることができる。青年と犬が生命を通い合わせている。そこにぼくたちの生を通わせることができる。一篇の詩のなかで、みんながつながってしまう。ぼくがイメージする「表現」とはそのようなものだ。「いい感じのもの」を共有することでつながり合う関係、それがぼくの欲しい「表現」だ。
こうした感じの良さは、うまく性を表現できていることから来ている気がする。この「ネロ」という詩の二人称で紡がれていく言葉には、前にも書いたように嘘臭さがない。作者と言葉と犬のあいだに隙間がない。この緊密さが、作品を成功させている。ぼくたちが心地よいと感じ、「善きもの」と直感するのは、みんな二人称の世界、いわゆる「性」に由来しているのではないだろうか。本来はかたちのない「性」を、かたちとしてうまく取り出せたものを「表現」と呼んでいいような気がする。
人間は木とも犬とも性的な関係を取り結ぶことができる生き物だ。取り結ばざるを得ない存在だ。それが人間にとって「生きる」ということなのだろう。人間の人間らしい生とは、見ることも触ることもできない「性」によって触発され、賦活されるものであり、この仕組みを言葉や色や形や音によって表現したものが、ぼくたちに「いい感じのもの」としてやって来るのだと思う。(2017.2.22)