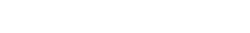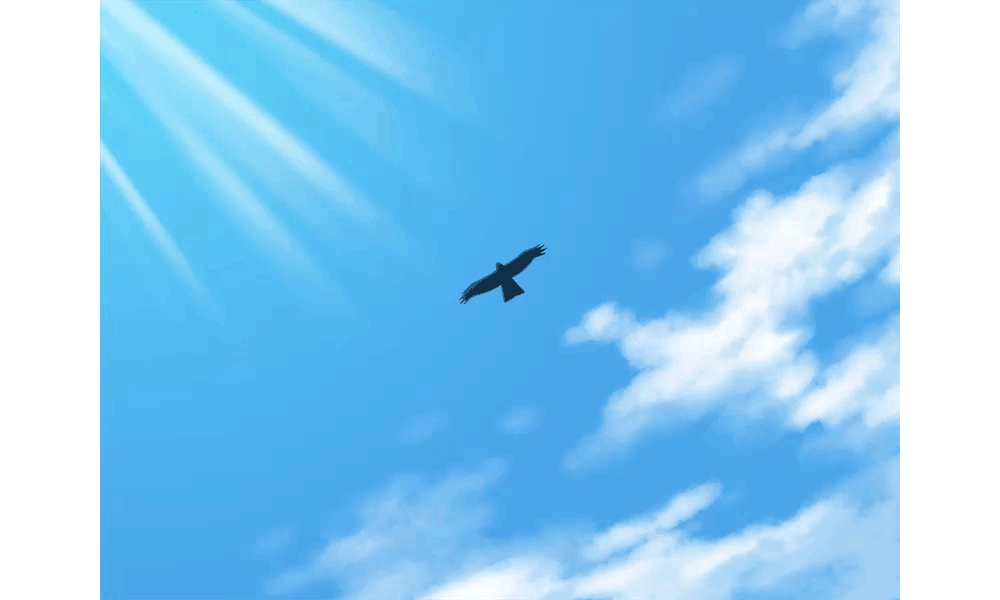1
2023年1月に亡くなった森崎茂さんとは、大学院生のときに知り合い、以後、濃淡や一時の断絶はあれ40年にわたってお付き合いさせていただいた。22、3の青年が60過ぎのおじさんになる歳月、小説を書いたり他の文章を書いたりすることが、ほぼ森崎さんの言葉の影響下にあったことになる。
1949年に熊本で生まれた森崎さんは、九州大学農学部を卒業後、東京で鍼灸の学校に通い、その後、福岡に戻って鍼灸院を開院された。はじめてお会いしたのもこのころである。森崎さんが福岡ではじめられた読書会に、ある人の紹介で参加したのがきっかけだった。月に一回、彼の自宅に十人ほどが集まり、フーコーやラカン、ソシュールといった主にフランス現代思想や構造主義の文献を読んだ。いま思い返すと、かなり高度な読書会だった。
読書会が自然消滅したあとも森崎さんとの関係はつづき、とくに2014年から5年ほどは、彼が住んでいた熊本と福岡のあいだを相互に行き来して、毎週とか隔週といった頻度で会っていた。そこでの森崎さんの話を編集し、『緊急討議・ことばの始まる場所』(全6回)と『連続討議・歩く浄土』(全5回)を電子書籍化して出版することができた。ほとんど熱に浮かされたように疾走しつづけた5年間だった。
2018年3月、森崎さんは心筋梗塞で入院。さらに5月には脳出血に見舞われる。以後、体調は思わしくなく、数年間はお会いする機会もなかった。それでも森崎さんはブログを更新しつづけ、また頻繁にメールのやり取りもしていた。亡くなる前年の2022年には熊本で二回お会いし、奥さまもまじえて一緒に食事をすることができた。しかし翌2023年1月8日、「いつ何があってもおかしくはありませんからね」と言われていたとおり、森崎さんは突然亡くなってしまう。最後のメールは亡くなる5日前のもので、今年は往復書簡をやって電子書籍として出版しましょう、という内容だった。
鍼灸師のかたわら、森崎さんは「内包論」と総称される論考を、約四十年にわたって書き継いでいった。「領域としての自己」「内包自然」「還相の性」「存在の複数性」といったオリジナルな概念を創出しながら、全円的な生のあり方、他者を自己の生存の手段としない世界のあり方を考えつづけたもので、その全貌はいまだ読み解かれないまま、豊饒な思想の大地をなしている。この「内包論」について概説しようというのがここでの趣旨だが、ぼく自身が充分に理解しているとは言えず、さらにそれを平易な言葉で伝えようとするのは至難の技で、書きはじめる前から途方に暮れている。
2
ぼくたちが頻繁に会って話をはじめた2015年2月ごろから、森崎さんは「歩く浄土」という論考を自身のブログに発表するようになる。亡くなる前年の2022年11月まで、あわせて282回分が公開されている。正確に数えたことはないけれど、ざっと計算して400字詰め原稿用紙で7000枚くらいになるかと思う。この膨大な論考で、彼はその時々の出来事について発言しながら、メインテーマとして「内包」の思想を深め、彫琢しつづける。
最初から最後まで、まったくぶれがない。照準がぴったり合っている感じだ。さまざまな角度、切り口から「内包」が論じられているわけだが、それはどういうものかとたずねられると、ひとことで説明するのはとても難しい。
けっして共同化できないようなそれ自体、それ以外のものではありえないような出来事は、わた しがわたしでありながらあなたである、そのような場所です。この場所を内包と言います。その場所へと媒介するものが還相の性です。それよりほかにわたしは生きることができませんでした。ここまでくるのにながい時間がかかりましたが、じぶんを生きるということは、生の原像を根源の性で生きることにほかなりません。わたしにとって生はそういうものとしてあります。(「歩く浄土2」2015.2.4)
初期の論考だけに、シンプルな言い方で内包が語られている。また個人的な体験を言葉にすることのほとんどなかった森崎さんが、ここでは珍しく自身の「体験」に触れている。内包の思想がどういうところから生まれたのか、かなり率直に語られている。それによると内包は、彼自身が生きるためにつくり出した思想であり、考え方である。たとえて言えば、なんとか息をするために手ずから開発した空気のようなものである。誇張を嫌う人だったから、「それよりほかにわたしは生きることができませんでした」というのは、言葉どおりに受け取るべきだろう。
おそらく森崎さんのなかでは、自分の言いたいことはこの数行に尽きているという思いがあっただろう。とりわけ、「けっして共同化できないようなそれ自体、それ以外のものではありえないような出来事は、わたしがわたしでありながらあなたである、そのような場所です」という短い文章によって、ほとんど内包は言い尽くされている。しかしそれがどういうことなのか、あらためて言葉にするために原稿用紙7000枚の論考を要した。ご本人が生きていれば、まだまだつづいていたはずだ。それほど彼が遭遇した体験は広くて深いということだろう。
どのように広くて深いのか? 「わたしがわたしでありながらあなたである、そのような場所」の広さと深さである、とひとまずは言うことができるだろう。本人のなかには間違いなく、そこに触れたという実感があった。この実感こそが、彼に40年にもわたって一つのテーマで書きつづけるエネルギーを与えた。体験としては一瞬だったかもしれない。一瞬の永遠を生きるために書きつづけた。「それよりほかにわたしは生きることができませんでした。」
わかったような気がして、すぐにまたわからなくなるのが内包論である。とくに「わたしがわたしでありながらあなたである」というフレーズの、わかったようなわからなさ感は格別である。こうしたわかりにくさは一般相対性理論や量子物理学と似ている気がする。むしろ数式化できない点では内包論のほうが手ごわいかもしれない。しかし本当は、これほどシンプルでわかりやすいことはないという気もする。
いつか森崎さんがブログで一つの逸話を紹介したことがある。ネットで見つけたという記事は、「硫黄島へ手紙『98歳 元気です』認知症の母、亡き夫へ」と題され、おおよそ以下のような内容だった。78歳になる元小学校教諭の男性が、自宅で年賀状を書いていると、認知症を患っている98歳の母親が、隣に坐って毛筆で手紙を書きはじめた。「硫黄島 笠原喜久治様 98歳で元気です 平成24年 笠原良久」という文面だった。その後、母親は脳出血で倒れ、半年後に亡くなる。亡母の部屋から見つかったメモには、夫が出征した日付や、硫黄島から手紙を受け取った日付などがまとめられていた。(「朝日新聞デジタル」2015年2月23日)
社会化された事実だけを見れば、夫は70年前に硫黄島で戦死し、残された98歳の妻は認知症を患っているという、ただそれだけのことだろう。しかし良久さんのなかでは、まったく別のことが起こっていたように思われる。夫の戦死の報せを受け取った当初、良久さんは大きな衝撃を受け、深い悲しみを抱え込んだはずだ。この悲しみは、その後もずっと良久さんとともにあっただろう。悲しみこそが、戦死した喜久治さんだったと言ってもいい。
仮に、この悲しみを取り除くことができたとしよう。データのようにきれいに削除できた。それで彼女は元通り幸せになれただろうか? むしろ良久さんの心にはぽっかりと穴があいたのではないだろうか。そこには固有の悲しみというかたちで、戦死した喜久治さんがいるからである。長い歳月のなかで、良久さんのなかにある喜久治さんという悲しみは徐々に音色を変え、深みを増していった。そうして生涯の終わりに、「98歳で元気です」という場所にたどり着いた。これはいったいどういうことだろう?
社会的な婚姻関係は、夫か妻か、どちらかの死によってひとまず解消される。このとき実体としてのつながりは失われると言っていい。しかし残された者のなかでは何かが生きつづける。目に見えない関係性のようなもの、いつまでもぬくもりを失わないつながりのようなもの。「根源の性」と呼ばれているのは、そのようなものではないだろうか。
自力の果てるところに還相の性はあります。わたしたちはその根源の性からのまなざしによぎら れ、その呼びかけに応えるだけです。わたしはそこが歩く浄土の場所だと思います。見ることも触ることもできませんが、絶えざる受動性としてこの〈ことば〉の場所はあります。それはいつもそこにあります。(「歩く浄土8」2015.2.14)
死者を取り戻すことはできないという意味で、大切な者の死において誰のどんな自力も尽きている。だがそれで終わりではなく、その先に「還相の性」があると森崎さんは言う。なぜなら大切な者を失った彼や彼女のなかには「根源の性」と呼ばれるつながりが残りつづけているからである。このつながりは自力のはからいではない。自力を超えたはたらきかけである。「わたしたちはその根源の性からのまなざしによぎられ、その呼びかけに応えるだけです。」
往路の恋にたいする、復路の恋とでもいうべきものを想定できるように思う。つまり還りみちの恋である。往きみちの恋は相手の不在によって終わる。だが終わることによってはじまるものがある。それが還りみちの恋で、不在になった相手からの呼びかけに応えることが、恋の内実となる。良久さんの場合も、「根源の性からのまなざしによぎられ、その呼びかけに応える」ことで、戦後70年を生きてきたのだろう。そうして生涯の終わりに、「98歳で元気です」という場所にたどり着いた。
この場所は、けっして一人ではたどり着けなかった場所だ。亡くなった夫・喜久治さんからの呼びかけに応えることで、たどり着いた場所だ。そこでは良久さんが喜久治さんによって表現されている。そして良久さんでも喜久治さんでもないものになっている。レオ=レオニの絵本で「あおくん」と「きいろちゃん」が遊んでいるうちに「きみどり」になってしまったように。良久さんは「わたしがわたしでありながらあなたである、そのような場所」にたどり着いたのではないだろうか。
ここには死の影がない。ぼくたちが知っている虚無や絶望としての死は姿を消している。かわって温かみのある、音色いいものが流れている。それは宮沢賢治が『注文の多い料理店』の「序」で、「わたしたちは、氷砂糖をほしいくらゐもたないでも、きれいにすきとほつた風をたべ、桃いろのうつくしい朝の日光をのむことができます」と描いている世界に近いかもしれない。
3
医学や自然科学が語る死には微塵の固有性もない。だからそこで語られる死は虚無と絶望に塗り固められ、ぼくたちが自力でなしうることは延命以外になくなるのだろう。たとえば医学が定義する死は、心肺停止にしろ、脳死にしろ、細胞死にしろ、要するに肉体の不可逆的な機能停止をもって死とするということで、この点は人も動物も変わりがない。なんと不条理な! 人は人であって動物ではない。そもそも動物には「死」という観念すらないだろう。「死」という観念をもつか否かが、人と動物の根源的な差異であると考える思想家もいる。にもかかわらず、死にかんしては人も動物も等し並みに扱われる。キリンやオットセイと同じ死が、人間にもあてがわれるのである。
フーコーによれば、臨床医学の本質は見ることであり、知覚されたものへの回帰によって特徴づけられる。その誕生は18世紀末から19世紀初頭とされる。
そこで問題とされる個人は、病める人間というよりは、むしろ、あらゆる同病者において無限に 再現しうる病理的事実なのである。(中略)医学の前にある任務は、一つの開かれた領域での、もろもろの事件を知覚すること、しかも無限に知覚することなのである。(ミシェル・フーコー『臨床医学の誕生』神谷美恵子訳)
18世紀末に生まれた臨床医学が対象とするのは病理的事実であり、疾病的地平という新たに開かれた領域である、とフーコーは述べる。この領域が可視化されるためには、個人が差し引かれなくてはならない。つまり「彼」や「彼女」を考慮に入れてはならない。病人は括弧に入れられる。それによって病気そのものが前景化し、病理的事実という可視的な領域が医学的なまなざしの前に開かれる。
なるほど、パンデミックは臨床医学(現代医学)が生み出しているわけだ。そこでは人種も国籍も宗教も問題にされないのだから。性別も無視されるのが普通である。ほとんどの手術において、男女によって術式が変わることはない。もちろん彼や彼女がどんな人生を歩いてきて、どんな考えをもっているか、といった個別性は考慮に入れられない。花が好きであろうとなかろうと、猫を飼っていようがいまいが、末期のがんにたいする処方は同じである。
こうして患者は固有性を差し引かれ、たんなる病理的事実として同一平面上に開陳される。この可視的な領域が、いまや全人類にまで拡大されようとしている。70億とも80億ともいわれる膨大な事例において無限に再現されるものだけが、臨床医学的なまなざしによって粗視化される。そのスケールが、いまや分子レベルになろうとしている、ということだろう。分子レベルで見れば、100億だろうが200億だろうが、個人の人種、国籍、宗教、思想、性格、感情などはすべて捨象できる。
ここにはどんな固有の物語も生まれない。キューブラー・ロスのいう死の受容モデルが、ほとんど誰にでも例外なしに観察されるのはそのためだろう。彼女によれば、死に瀕した者は共通して五つの段階をたどる。まず否認と孤立の段階があり、つぎに怒り、さらに延命のための取引を試みる時期があり、それが過ぎると抑鬱や悲嘆がやって来て、最後の受容に至る。
受容を幸福な段階と誤認してはならない。受容とは感情がほとんど欠落した状態である。あたかも痛みが消え、苦闘が終わり、ある患者の言葉を借りれば「長い旅路の前の最後の休息」のときが訪れたかのように感じられる。(中略)死に瀕した患者は、いくばくかの平安と受容を見出すが、同時にまわりに対する関心が薄れていく。一人にしてほしい、せめて世間の出来事や問題には煩わされたくないと願う。(E・キューブラー・ロス『死ぬ瞬間』鈴木晶訳)
なんとも貧寒として、寂しく、痛々しい死ではないか。どんな人生も、最後には抑鬱と悲嘆が待っている。あたかも命の泉が尽きるように、感情を欠落させ、人は一人で自分の死を受容して死んでいく。これでは世界中がニヒリズムに塗りつぶされてしまう。老い先短い年寄りはともかく、若い人はとても生きていけない。
いつか家族でヨーロッパへ行ったとき、バスでレマン湖のほとりを走っていると、ツアーのガイドさんが「このあたりにオードリー・ヘップバーンの別荘があります」と説明してくれた。スイスでは安楽死が合法化されているために、幾つもの自殺ほう助団体がある。ディグニタスとかイグジットとか、冗談みたいな名前の付いた団体の本部がチューリッヒかどこかにあったはずだ。「安楽死ツーリズム」なるものが企画されており、世界中から安楽死を求める人たちがやって来る、という話を聞いたことがある。
ヘップバーンが安楽死のことを考えてスイスに家を持っていたのかどうか知らない。しかしスイスが世界中の大金持ちにとって眷恋の地である以上、彼らが最後に望むことの一つが安楽死であることは間違いないだろう。有り余るほど金があって、その金で何をしてもいいと言われると、選択肢の上位に安楽死が入ってくる。どうも根本的に、ぼくたちは何かを間違っている。人間は人間を間違っているという気がしてくる。
晩年のインタビューのなかで吉本隆明が、原始キリスト教や原始仏教の聖書や聖典は、いま読むと立派なものだし、われわれには到底考えられないようなことが書いてあるけれど、人類史を広く数百万年の長さでとらえたとき、現世の聖人君子が編み出した宗教は相当堕落しているのではないか、という趣旨のことを述べている。
アフリカや南アメリカの先住民がシャーマニズムのようなものとして保存している古い精神のかたちには、死という概念が少しも含まれていない。文化史時代の宗教の元祖が生死の概念をつくる以前には、生死の概念はない。そのほうが人類史的にはるかに立派で、本当だと思わせる。「そういうことを考えると、ホスピスや安楽死というのは、もう下の下、堕落の極地みたいな考え方だと、どうしてもなります。」(『老いの超え方』)
どうやらぼくたちの遠い祖先は、生死の概念のない時代を長く生きてきたらしい。人間が死に取り憑かれて生きるようになったのは、原始仏教や原始キリスト教からかぞえても、せいぜい数千年から一万年くらいのことで、人類史からするとごく最近のことである。その死が、現在では貨幣とともに最強の共同幻想になっている。それは科学が最強の新興宗教になっているのと同じである。
なぜ人類は「死」にとらわれるようになったのだろう? おそらく「自己」なるものを起点として世界を考えるようになったからだろう。仏教にしてもキリスト教にしても、個人を単位として輪廻転生や魂の救済といったことが考えられている。個人の信仰や追善によって、天国や浄土に行けたり行けなかったりする。「わたしはわたしである」という同一性を生きることの拠点とすれば、どうしたって生と死はついてくる。グリコのおまけみたいにもれなくついてくる。
熱力学的に考えてみよう。自己という閉じた系のなかではエントロピーが増大していく。赤ん坊のエントロピーは低い。老人のエントロピーは高い。過去はエントロピーの低い状態で、未来は高い状態である。こうして不可避的に、加齢とともにエントロピーは増大し、ある閾値を超えて自己という同一性の秩序を保てなくなったとき、人は死ぬ。なんと、仏教であれキリスト教であれ、人が死ぬことは、カップのなかでコーヒーが冷めていくことと同じなのである。そりゃあ吉本さんでなくても、「現世の聖人君子が編み出した宗教は相当堕落している」と言いたくなる。
死の概念が、聖人君子が編み出した宗教とともに生まれ出たものであるのなら、それは宗教と同じように共同幻想である。もちろん貨幣も科学も共同幻想である。つまり虚構であり、フィクションである。その証拠と言ってはなんだが、昔は貝殻がお金だった。だから「貨」とか「財」とか「買」とか、お金に関係する漢字にはみんな「貝」が入っている。それが貴金属になったり紙切れになったりして、いまはデジタル暗号みたいなものになろうとしている。こんなふうにお金には実体がない。その社会、その時代の人々が信じているものがお金になる。
死も同様である。たとえば『源氏物語』のなかで、紫の上が一時的に亡くなる場面がある。報せを聞いて、光源氏が慌てて院へ戻ると、すでに僧たちは病気平癒の祈祷のための檀を壊して退出しはじめている。院では紫の上に仕えていた女房たちが泣き騒いでいる。しかし諦めきれない光源氏は、ダメ元で大がかりな加持をさせる。すると紫の上に取り憑いていた物の怪が調伏されて、死んだはずの彼女は生き返る。こんなふうに平安時代の死は「ご臨終です」で終わりではなかった。「殯宮」(もがりのみや)にしても、亡くなって数ヵ月は死が確定しないので、そう特別な建物に安置して、遺体が腐敗・白骨化していくのを確認したのだろう。天皇などの場合は一年間ほど置かれたというから、すさまじいものだ。
その時代の、その社会の死がある。つまり死はフィクションである。虚構だから、消すことができる。どうやって? たとえば「98歳で元気です」の老女のようにして。その人にとって固有の場所を生きるとき、おのずと死は消えているのではないだろうか。ところで固有性というのは、森崎さんも言っているように、自分一人ではつくり出せない。かならず他者からの働きかけがあり、それに受動的に応答することで生まれてくる。こうして互いが互いにたいして表現をなすとき、死は消えていかざるをえないのだと思う。
4
森崎さんが亡くなる直前まで、どうしても書きたいと話していたのが「オチ・オサム論」だった。たしか2022年の秋ごろだったと思う。自分が長年考えてきた「内包」とオチ・オサムさんの「浮遊する球体」はまったく同じものであることに気づいた、という内容のメールを受け取ったおぼえがある。まさに「発見!」という驚きと喜びが伝わってくるような文面だった。
画家オチ・オサム(1936~2015)については、ご存じない方も多いだろう。福岡を拠点とする前衛美術グループ「九州派」の創設者の一人で、1950年代末にアスファルトや日用品を表現の素材とした作品で美術界に登場して以来、孤高の存在として独自の絵画空間を生み出しつづけた。その彼が1960年代後半から亡くなるまで描きつづけたのが、森崎さんの注目した球体の絵である。全部で四百点ほど制作されたらしい。絵のサイズは50号から300号と大型のものが多い。二枚とか四枚とか、偶数枚を一度に制作することが多かったようだ。50号のカンバスを二十枚も並べ、地塗りから同時進行で4~5年かけて仕上げられた作品もあるという。
デッサンなどはせずに、カラス口を使ってカンバスに直接描いていくというやり方だったらしい。カラス口というのは、先端にカラスの嘴のような金属製のパーツがついたペンで、細くて均一な線を引くことができるため、主に製図などで使われる。これをコンパスに装着して、先に薄く溶いた絵具を垂らすように忍ばせてアウトラインを描く。さらに面相筆で薄く、薄く球面を塗り重ねていく。「ルネサンス期の宗教画のような緻密で気持ちのこもったマチエールを探求しておりました」と夫人は述懐しておられる。
これらの絵に、なぜ森崎さんが注目したのか、最初はよくわからなかった。自分が長年考えてきた「内包」と同じものであることに気づいたというのだが、球体ばかりが描かれた絵と、森崎さんの内包がどこでどう結びつくのか。なんとなく「そういうことではないか」と思うようになったのは、ジル・ドゥルーズの「ミシェル・トゥルニエと他者のない世界」という論考を再読したことがきっかけだった。
この文章はもともと、ミシェル・トゥルニエの『フライデーあるいは太平洋の冥界』(榊原晃三訳)という小説の書評として発表された。題名からも推察されるように、トゥルニエの小説はダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』を下敷きとしたものだが、デフォーのロビンソン物語が、孤島で一人暮らしをする男が自らを秩序的に律し、難破船からの漂流物などを利用して、原始的な経済世界を構築していくさまを描くのにたいし、トゥルニエのロビンソン物語では、同じ境遇に置かれた男のたどる道筋はかなり錯綜している。そこには退行があり、倒錯があり、神秘主義的な昇華がある。
この奇妙なロビンソン物語に寄り添いながら、ドゥルーズは「知覚を可能にするものは自我ではなく、構造としての他者である」と述べる。
他者は、私の知覚の領域における対象でもないし、私を知覚する主体でもない。それはまず第一 に知覚領域の構造であって、それがなければ、知覚領域の全体が適切な機能ができなくなるだろう。(岡田弘・宇波彰訳『意味の論理学』所収)
トゥルニエのロビンソン物語は、こうしたアプリオリな他者の構造が崩壊していく過程を描いている、というのがドゥルーズの読みである。世界の構造から他者が欠けると何が起こるか? 世界は、いまわれわれが見ているように見えなくなる。諸事物は客観的に立ち現れなくなる。なぜなら「私」は対象に貼りついてしまい、自分と対象は区別できなくなるからだ。意識と対象は一つになってしまい、二つは分離できなくなる。いま自分の見ているものだけが世界になるから、誤謬の可能性もなくなる。世界から潜在性や可能性が失われ、あらゆるものが剥き出しになる。背景も手前もなく、事物は起伏を捨てて二次元の線に還元される。意識と対象は現在のなかで癒着してしまい、時間は前にも後ろにも流れなくなる。そして屹立した「いま」だけが永遠につづく。
これこそ倒錯者の世界である、とドゥルーズは言う。サディストに欠けているのは他者の構造である。彼らは犠牲者を「苦しめる相手」として見ることができない。犠牲者は共犯者でもあり、自分の分身でもある。
倒錯者の世界は他者のない世界であり、したがって可能的なもののない世界である。他者とは可 能にする者のことである。倒錯的な世界では、必然的なもののカテゴリーが可能的なもののカテゴリーに完全な代わりになった世界である。(中略)すべての倒錯は他者を殺すこと、他人を殺すことであり、したがって可能的なものを殺すことである。(ドゥルーズ、前掲書)
これはキューブラー・ロスがチャート化した死の受容モデルにも、そっくり当てはまるだろう。「死に瀕した患者は、いくばくかの平安と受容を見出すが、同時にまわりに対する関心が薄れていく。一人にしてほしい、せめて世間の出来事や問題には煩わされたくないと願う。」そんな彼のいる場所には可能性がない。可能性はすべて必然性に置き換わっている。まさに他者のいなくなった世界、倒錯者の世界である。
なぜこんなことになっているのか? なぜこんなものを「死」として受け入れなければならないのか。もっとやわらない、温かみのある死を発明しようではないか。「98歳で元気です」のおばあちゃんのように、「死が消える場所」を一人ひとりが手づくりできないだろうか?
テーブルの上に置かれたリンゴやミカンが立体的なものとして見えるのは、ドゥルーズによればアプリオリな構造としての他者のおかげである。この構造を欠いたとき、果物は肉体を奪われて線に還元される。そこに立ち現れるのは、厚みも奥行きもない寒々とした世界だろう。キューブラー・ロスが観察している「死に瀕した患者」は、おそらくそうした世界を生きている。
オチ・オサムの作品は、純粋な球体だけを描いている。そのためリンゴやミカンが描かれた静物画よりも、禁欲的な感じを受ける。一連の球体シリーズについて、画家本人は「恐怖が描かせた祈りみたいなもの」とインタビューで答えている。「毎日、何かしら描いている後ろ姿は修行僧のようでした」と夫人も回想しておられる。残された言葉とは裏腹に、絵の印象はけっして暗くない。青、緑、紫、ピンク、オレンジといった明るい色調で描かれた大小の球体は、いずれも淡い光沢を帯びて、視覚的に軽やかで愉悦的な感じを与える。
ここにはドゥルーズがいうところの、アプリオリな構造としての他者の問題が、より本質的に提示されているように思う。二次元のカンバスに描かれた円は、なぜ球体に見えるのか? いくら巧妙に描かれていても、見る者はそこに描かれているのが二次元の形象に過ぎないことを知っている。にもかかわらず、丹念に色を塗り重ねられた円を、ぼくたちは球体として見る。むしろ二次元の円として見ることのほうが難しい。どうしても球体に見えてしまうのである。
個人の一つの視点からは、球の裏側も側面も見えないはずだ。自己や主観にとって、実際に見ることのできない対象の部分は、潜在性や可能性にとどまっている。この潜在性や可能性を展開して、ぼくたちは「球体」という知覚をつくり出している。そこにはドゥルーズがいうところの他者の構造が関与している。
私が見ることのない対象の部分を、私は同時に他者には見えるものであると考える。したがって、私がその隠れた部分に到達するためにひとまわりすると、対象の裏側にある他者と出会い、対象の全体を予見できるようになるだろう。(ドゥルーズ、前掲書)
「見る」という何気ない行為において、すでに他者が駆動しているのである。二次元のカンバスに描かれた円が球体に見えるのは、それをともに見ている者がいるからだ。このアプリオリな構造としての他者は、実体ではなく可視化することもできない。しかし常に自己や主観の手前にいて、ぼくたちに世界をもたらしてくれている。背後も手前もある、この世界をもたらしてくれている。潜在性と可能性を内包した、厚みと奥行きのある世界をもたらしてくれている。
いわば「生」を可能にしている目に見えない構造を、森崎さんはオチ・オサムの「浮遊する球体」の絵に見出したに違いない。そして自分が長年考えてきたことと同じだという発見と驚きをおぼえただろう。なぜならオチ・オサムの絵を見るとき、おのずと内包の場所で見ていることに気づかされるからだ。ぼくたちが何かを見ることは、「わたしがわたしでありながらあなたである」という内包のまなざしで見ることである。そうでなければ、世界は現にあるようには立ち現れない。「見る」ことは、自己や主観を遥かに超えた行為なのである。
だから見ることには「美しい」という感覚が伴う。食べることには「おいしい」という味覚が伴う。いずれも一人ではつくり出せないものだ。ともに見ている者がいるからこそ、ぼくたちが生きている世界は美しいのである。ともに味わう者がいるからこそ、世界は賞味すべきものになる。人が生きることのなかに、自己や主観に封じ込められるようなものは、ほとんど何もないと言っていい。生きることは、常に「ともに」であり、誰もが知らないうちに「わたしがわたしでありながらあなたである」という内包的な自然を生きている。
世界が美しいものやおいしいものに溢れていること。つまり喜びに満ちていること。それこそが、ぼくたちのなかで常に内包的な自然が息づいていることの証である。この自然の上に、個人、貨幣、宗教、国家、科学といった、もう一つの自然が上書きされていく。上書きされた自然のなかに、美しいものやおいしいものが生まれる契機はない。貨幣や科学をいくらつつきまわしても「美しい」や「おいしい」は生まれてこない。したがって喜びも悲しみも生まれない。なぜ大切な人の死は残された者に深い悲しみをもたらすのか。個人や宗教や国家からは説明ができない。
上書きされた自然の特徴は、可視化され実体化されたものから成っていることである。それはA=Aという同一性によって粗視化された自然であり、内包的な自然にたいして外延的な自然と呼ばれる。「外延的」というのは、たとえば個人を単位として考えると、個人と個人が結びついて夫婦になり、家族をなし、家族が結びついて共同体になり、信の共同性として宗教になり、国家になり、その過程で貨幣が発明され科学が生まれ、それがさらに人と人を結び付け、というふうに外延的に拡大していくからである。
この外延的な過程が行き詰っている。個人も貨幣も宗教も国家も科学も、あらゆる場面で行き詰っている。ぼくたちの生は利便性や快適さや効率といった実体化されたものに取り囲まれ、「喜び」とはほど遠いものになっている。可視化された生は、「健康」という善のもとに遺伝子レベルで管理され、可視的になった一人ひとりの生の価値は、計測され、序列化される。その果てに、孤独と絶望に満ちた死が待っている……という具合に、外延的な自然はどこまでも行き詰っている。
しかし案ずることはない。誰のなかにも内包的な自然がひっそりと息づいているから。医学や生物学が切り取る外延的な死とは別に、一人ひとりが固有の死を手づくりすることができる。それは外延的な死にたいして、内包的な死と呼ばれるだろう。
わたしたちが認識の自然としている思考の慣性を転倒すると外延的な死は内包自然のなかで内包自然という生の一部となる。死はわたしに属することでも、共同幻想に属すことでもなく、根源の二人称の分有としていつも生きられている。(「歩く浄土275」2021.3.18)
5
固有性とは何か? 固有の体験を他人に語って聞かせることはできない。つまり内面化という社会化された意識のあり方で表現することはできない。内面化も社会化もできないから固有なのである。言語化できない体験は、いつまでもその人を去らない。逆に言えば、言語化したときには、すでに体験はその人を離れ、本来の固有性は失われている。
多くの被爆体験が言語化され、いわば内面の劇として表出されている。それを読むぼくたちは、内面の共同化という擬制以外のものは何もないと感じる。したがって何も伝わらず、言葉を発する者と、その言葉を受け取る者がつながることはない。固有性は語りえないものとして、その場に取り残される。
死は、一人ひとりにとって固有の体験である。だから言語化できない。キューブラー・ロスによれば、死に瀕した者は否認し、怒り、延命を試み、抑鬱と悲嘆にとらわれ、自力が果てたところで死の受容に至る。個人を最小単位とした外延的な自然の枠組みで考えるかぎり、そうしかならない。誰もが死という固有の場所に、孤独と絶望とともに取り残される。しかし誰のなかにも内包的な自然が息づいているとすれば、この固有の場所を内包的な息づかいによってひらくことができるはずだ。
自力が尽きているはずの体験が、稀にひらかれていると感じる場面に出会うことがある。不思議なことに、そこにはかならす〈性〉のぬくもりが感じられる。自己の固い殻を破って、「わたしがわたしでありながらあなたである」という、内包の場所が表出されているように感じられるのだ。
たくさんあるから はんぶんあげるね
はんぶんになっても まだたくさん
まだあるから はんぶんあげるね
すこしへったけど まだあるから
そのまたはんぶんあげるね
とうとうあとひとつになってしまったけど
それでもはんぶんにわってあげるね
つぎにきたこには もうわけてあげられないから
のこったはんぶんの ビスケットをあげるね
ぜんぶあげちゃったけれど
ビスケットとおなじかずの
やさしさがのこっているよ
(堀江菜穂子「たくさんのビスケット」)
本の帯には「脳性まひとたたかう“声なき詩人”」というキャッチ・コピーがあり、その下に「寝たきりのベッドで紡いだ『心』を呼び覚ます54編」と説明がある。これでだいたいの事情はわかる。わかりやすさを狙ってつくられたコピーでもあるだろう。ぼくたちもそうしたわかりやすさを踏まえて読むわけだが、この詩の良さは「わかりやすさ」を超えている。帯の文言などどうでもいいと思わせるようなものだ。
技術的には、けっして高級なものではない。子どもっぽいし、稚拙といえば稚拙かもしれない。しかしそんなこととはまったく無関係に、この詩は何かを届けてくれる。それは文学性や芸術性といった擬制を突き抜けて、はるかに本質的なものだと思う。その本質的なものを言葉にするのは難しい。ただ何か、言葉の手前にある「善きもの」が表出されているように思える。
彼女が詩を書いたことは、本当は二義的なことなのだと思う。たとえ詩を書かなくても、そこに詩は生まれている。寝たきりのベッドの上で。詩はどこで生まれるのか? 「わたしがわたしでありながらあなたである」という、内包の場所でだと思う。
あの猫のことはどう言ったらいいんでしょう。僕にとって特別な猫であることはまちがいないんだけれども、じゃあ、どんなふうに特別であったかを言葉にしようとすると、これといって特別なところはなんにもなかった。でも自分の執着のしかたを見ていると、やっぱり何かあるんですよ、きっとね。
犬たちに吠えられて屋根のいちばん高いところでぼんやりしているフランシス子を見ていると、僕は自分がそうしているような、なんとも言えない気持ちがしました。
結局どこにもいくことができずに出戻ってきた猫だったのに、どういうわけか、僕が一生懸命かわいがったら一生懸命なついてきて、しまいには猫の生活か、人間の生活か、わからないほどになってしまいました。
僕は、自分の子どもに対してもそういうかわいがりかたはしなかったと思う。長年連れ添った夫婦であっても、ここまでのことはないんじゃないか。そのくらい響きあうところがあった。
もう、この猫とはあの世でもいっしょだという気持ちになった。この猫とはおんなじだな。きっと僕があの世に行っても、僕のそばを離れないで、浜辺なんかで一緒に遊んでいるんだろうなあって。
(吉本隆明『フランシス子へ』より抜粋)
ここでも詩が生まれていると感じる。ここに読まれるのは詩人の言葉でも、思想家の言葉でもない。強いて言えば、宮沢賢治がなりたかった「デクノボー」によって発せられた言葉である。それにしても、なんともうれしくなるようなデクノボーぶりではないか。彼はいかにしてデクノボーになったか? フランシス子という一匹の猫によってである。ご本人もおっしゃっているように、とくにどうということのない猫だったのだろう。しかし吉本さんにとっては、取り替えのきかない「この猫」だった。猫以上の存在だった。「この人」と言ってもいいかもしれない。「長年連れ添った夫婦であっても、ここまでのことはないんじゃないか。そのくらい響きあうところがあった」なんて、すごいなあ。奥さんの目に触れていなければいいのだが。
デクノボーとしての吉本さんは、彼が長年考えてきた非知や非僧非俗を突き抜けて、愚それ自体、俗それ自体、卑小であることそれ自体になっているように思える。生は固有なものとして伸びやかになっている。デクノボー化した吉本さんは、どこへだって行くことができる。むしろ思想家としての吉本隆明は、どこへも行けない人だったのかもしれない。状況に屹立した彼のまわりには、多くの迷える若者たちが集まってきた。そういうところは親鸞と似ている気がする。そして最後の親鸞が非僧非俗の場所に赴いたように、吉本さんはデクノボーになった。
いいなあ。自由だなあ。どれくらい自由かというと、「もう、この猫とはあの世でもいっしょだという気持ちになった」というくらい自由である。
喰い、寝て、念ずる生の原像を還相の性で生きればいつでも歩く浄土が姿をあらわすのです。(「歩く浄土26」2015.3.16)
生の原像を還相の性として生きるとき、だれにとっても、一人ひとりの生の固有性が凡俗の極み としてあらわれる。この無上の出来事に生きていることの価値の源泉がある。(「歩く浄土259」2019.12.2)
たしかにそうだ。戦後最大の思想家は、最後の場所で凡俗の極みとなって生の固有性とともにある。そして彼のなかで、浄土は歩いている。とくにどうということのない、たった一匹の猫によって。それほど人間とは広いものだ。浅くて深いものだ。
ここでも死は消えている。「一人ひとりの生の固有性が凡俗の極みとしてあらわれる」とき、おのずと死は消えるのではないだろうか。誰もが、このような表現をなすことができる。なぜなら、誰のなかにも「始まりがあって終わりのない、ますます深くなる還相の性」がひっそりと息づいているからである。その場所を一人ひとりが自分のやり方でひらく。ときには言葉として、ときには沈黙として。一言も発しないことも、また大いなる表現である。
いつか城崎温泉へ行ったとき、宿で一組の老夫婦と出会った。ご主人は94歳ということで、足元がおぼつかない。杖をついて、夫人に支えられて歩いている。その夫人も、かなりの高齢と見受けられた。「これが最後かなと思って来ました」と夫人は言っていた。二泊三日の滞在中、何度か老夫婦に会った。何をしていたのかたずねると、一日目は部屋でのんびりしていたということだった。二日目は近くの温泉に行ってきたという。城崎の温泉街には、外湯という共同浴場が六つか七つかある。そのうちの宿から一番近い湯に行ってきたという。残り少なくなった時間を慈しむように、二人は静かに温泉街の春を過ごしていた。
彼らを「夫婦」という言葉で言い表すことはできないと思った。夫婦と言っても連れ合いと言ってもはみ出してしまうものがある。それこそ名づけようのない「無上の出来事」として、二人はぼくの前にあった。まさに「生きていることの価値の源泉がある」と感じられる出来事として、寄り添って廊下を歩いたり、食事処でひっそりと食事をしていたりした。
往きみちの恋に固有性はない。固有なものは還りみちで生まれる。死を生きることによって生まれる。たまたま出会った老夫婦のたたずまいを名づけようのないものと感じたのは、彼らのなかでは、生きながらにして、すでに双方の死が生きられていたからかもしれない。互いが互いにたいして表現をなすとき、おのずと死は消える。死は生きられるものになっている。
〈了〉