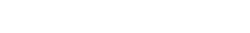第6話 遠いともだち①
解剖学者の三木成夫さんは、「原初の細胞ができてから後の、今日までの三十数億年の長い進化の過程を、なにか幻のごとく再現する、まことに不思議な世界」が「胎児の世界」であるとおっしゃっている(『生命とリズム』)。三十数億年! そんな長大な歴史を過たずに生きて、ぼくたちは生まれてきた。誰もがみんな母親の胎内で三十数億年を旅してきたのだ。
このように見てくると、人間のからだに見られるどんな〈もの〉にも、その日常生活に起こるどんな〈こと〉にも、すべてこうした過去の〈ものごと〉が、それぞれのまぼろしの姿で生きつづけていることが明らかになる。そしてこれを、まさに、おのれの身をもって再現して見せてくれるのが、われらが胎児の世界ではなかろうか。(三木成夫『胎児の世界』)
ニック・レーンは『生命、エネルギー、進化』のなかで、原核細胞から真核細胞が誕生するシナリオをプロトン勾配という概念を使って読み解こうとしている。いまから40億年ほど前に、深海のアルカリ熱水孔で無機物が有機物になったことで、生命の歴史は幕を開ける。このとき誕生した細菌の仲間は、なぜか以後20年億年くらいはほとんど進化しなかった。ところが15~20億年前に、細菌と古細菌の内部共生によって真核細胞が生まれた。生命40億年の歴史でただ一度だけ起こった、この奇蹟的な出来事によって、有性生殖や二つの性、死を免れない個体と不死の生殖細胞、といった不可解な特性が真核生物に備わることになった。
いくらか時間の幅はあるけれど、少なくとも十数億年の時間が、ぼくたちのなかを流れていることは間違いないようだ。この長大な時間を内包した生命として、ぼくもきみもあなたも日々を生きている。目に見えないし、通常は意識されることもない。でも、それは誰のなかにも流れている。三木成夫さんが言うように、「それぞれのまぼろしの姿で生きつづけている」のである。この「まぼろしの姿で生きつづけている」ものを、宮沢賢治は「遠いともだち」として、ユリアやペンペルという、どこか親しげで懐かしい名とともに取り出してくれているのではないだろうか。
おそらく賢治の童話に出てくる不思議な名前は、ぼくたちのなかに内包された時間の「遠さ」をあらわしている。たとえば「ジョバンニ」や「カンパネルラ」は、空間化すれば日本とヨーロッパ(イタリア)のあいだの距離に相当する時間的な「遠さ」をあらわしている。「ユリア」と「ペンペル」では、その遠方はほとんど空間化できない。「ペンネンネンネンネン・ネネム」になると、40億年前に生まれた細菌の名前といっても通用しそうだ。そんなこんな「遠いともだち」が、平気な顔をして賢治の詩や童話のなかを歩いている。(2017年12月15日)