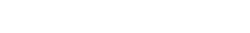第9話 「慈悲」について②
一口に仏教といっても、現在のタイやミャンマー、ラオス、カンボジアのような国々で信仰されているものと、中国経由で日本に入ってきた、いわゆる大乗仏教といわれるものとでは、中身がずいぶん異なるようである。釈迦牟尼ことゴータマ・シッダッタによってインドで創始された原始仏教には、生きとし生けるものへの憐れみ、といった発想はまったくない。釈迦族の王子として生まれたシッダッタは、父王によって花よ蝶よと、いわば箱入り息子状態で育てられた。そんなぼんぼんが青年になり、「四門出遊」というんですか、お城の外に出たところで病老死を目の当たりにしてショック状態に陥る。さらに病老死の苦しみから抜け出すために、この世の執着を捨てようとしている修行者の姿に心打たれ、自らも出家を決意した、ということに伝説ではなっている。
釈迦によって創始された仏教は、当初の動機からして、生病老死の苦しみを自覚した人の自己救済なのである。順序としては自利から利他であって、逆ではない。つまり「自分のための宗教」が「人々のための宗教」に変わっていったわけで、これが仏教の「慈悲」の考え方だとすると、それは最初から社会化されている。このやり方では「間に合わない」と賢治はあせったと思う。なぜなら彼には、もともと自他という区別がないからである。
たとえば賢治が「わたくしといふ現象は/仮定された有機交流電燈の/ひとつの青い照明です」「風景やみんなといっしょに/せはしくせはしく明滅しながら/いかにもたしかにともりつづける/因果交流電燈の/ひとつの青い照明です」(『春と修羅』序)と書くとき、彼は文字通り自他の区別のない場所を「わたくし」として生きている。それは彼が残した作品からして疑いのないことだ。賢治にとって「自己」とは実体ではなく現象である。
あるいは森崎茂さんの「領域としての自己」という用語を使わせてもらうべきかもしれない。
世界の了解線を内包へと冪乗すると、世界はべつのまなざしによって未知のものとして現前する。わたしより近いあなたをわたしとして生きると、自己は主体に付属する実体ではなく、領域としての自己としてあらわれる。(『歩く浄土』209)
賢治が「風景やみんなといっしょに/せはしくせはしく明滅しながら/いかにもたしかにともりつづける」というとき、「わたくしといふ現象」は閉じた一個のモナドに対比される「領域としての自己」になっている。しかも宮沢賢治という自己の領域は、十数億年に及ぶ「遠いともだち」を包摂したものとして広がっている。ほとんど世界を「わたくしといふ現象」として生きたと言ってもいいくらいだ。このような賢治の自己=世界は、やはり森崎さんがしばしば引用されるヴァイツゼッカーの、つぎのような覚知に近いかもしれない。
現実に生きられていない生命の充溢、それは現実に生きられ体験されているほんの一片の生命よりも、予想もつかぬほど豊かである。もしもわれわれが現実的なもの以外に、可能なるもののすべてに身を委ねたとしたならば、生命は恐らくは自己自身を滅してしまうことになるだろう。だからこの場合には、有限性は人間の悟性が遺憾ながら限定されたものであることの結果としてではなく、生命の自己保存の戒律としてわれわれの眼にうつる。(『ゲシュタルトクライス』木村敏・濱中淑彦訳)
実際に賢治は上京して印刷所でアルバイトをしながら田中智学の国柱会で布教活動に精を出し過ぎて身体をこわしたり、イモチ病の予防と駆除の指導に村々を奔走したあげくに疲労困憊して急性肺炎を起こしたり、まさに「自己自身を滅ぼしてしまうこと」との瀬戸際の生涯を、最後まで送ったように見える。それは仏教の修行僧などよりも過酷な境涯だったかもしれない。なぜなら賢治が生きたのは、「自己救済」などでは到底手がつけられないようn過酷さだったからだ。「悟り」や「解脱」によって片付くものは、何一つなかった。
慈悲は空観にもとづいて実現されるのであるから、慈悲の実践をなす人は「自分は慈悲を行っているのだ」という高ぶった、とらわれた心があるならば、それはまだ真の慈悲ではない。慈悲の実践は、慈悲の実践という意識をこえたところにあらわれる。(中略)すなわち現象的な自己を無に帰したとき、慈悲が絶対者からあらわれるのである。そうして慈悲行は個我のはからいではなくて、個我を超えた絶対者から現れ出るものなのである。(中村元・前掲書)
ここに見られる「空観」などという考え方を、最後の宮沢賢治は完全に否定しきっているように思う。それが「雨ニモ負ケズ」の強さだろう。実際、「現象的な自己を無に帰し」て済むような話ではなかった。賢治にとって仏教の戒律は、手ぬるいものだったに違いない。それは「戒律」に過ぎないからだ。すべての戒律は、ヴァイツゼッカーが言うように「生命の自己保存の戒律」である。「もしもわれわれが現実的なもの以外に、可能なるもののすべてに身を委ねたとしたならば、生命は恐らくは自己自身を滅してしまうことになる」。だから自己保存のために「有限性」という戒律を身にまとうのである。どんな高度な仏教者の修行も、そこから出発している。
宮沢賢治は戒律の手前を生きている。規範や禁止のはるか手前で「食べたくない」とか「犯したくない」とか言っているのである。なぜから「遠いともだち」がいるから。しかも彼らは自分よりも近くにいるから。例によって、ここで賢治のなかの「遠い」と「近い」は自在に変換している。内にあるものが外にあるものに、外にあるものが内にあるものに自在に変換するように。「遠いともだち」とともにある賢治の生はそうしたものだ。
仏教のなかにも肉食にたいする忌諱や禁忌はあるけれど、宮沢賢治の詩や童話、書簡などから伝わってくる直接性にくらべると隙間があり過ぎる。戒律による禁止は、自他の差異を前提としている。だから自己救済としてはじまったものが、たちまち空間化されて社会的な規範(権力)になる。宮沢賢治は自他という差異の手前を生きていたのであり、だから「遠いともだち」の痛みは彼にとって直接的である。賢治にくらべると、2500年前にお生まれになったシッダッタさんは、はるかにモダンという気がする。
(2017年12月22日)