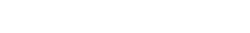第8話 「慈悲」について①
いかなる生けるものでも苦しんでいる限り、自分らは完全に幸福とはなりえないと感じる。修行者ほどの徹底性はないにしても、これは誰のなかにも多かれ少なかれある感覚だろう。状況にもよるけれど、いくらか気持ちに余裕のあるときは自然とそんなことを思う。なぜだろう? ぼくたちのなかに「遠いともだち」がいるからではないだろうか。だから有情にたいする「慈悲」の気持ちがおのずと湧いてくる。うん、そう考えよう。
宮沢賢治という一人の文学者が現れるまで、この「遠いともだち」のことを誰もうまく言い表すことができなかった。うまくつかむことができなかった。それで苦し紛れに「仏」などと呼ばれていた。大応国師(誰だよ、それ?)は、「まことの仏のことは、まえにくはしく申しつる如く、仏は衆生の心にあるなり。その仏は色もかたちもなく、大にもちひさき物にもなし、過去、現在、未来もなく、虚空の如くにていたずらといふ所なく、いきしになく、いやしくもなし、是れ根本の仏也」と言っている。これではなんのことかわからない。そこで否定性(~ではない)においてしか語りえない「仏」は、たとえば「菩薩」として可視化される。この「菩薩」を概念化すれば「慈悲」なる。
菩薩は、衆生の中に処して三十二種の悲(あわれみ)を(観音菩薩のごとく)行い、漸々に増広して転じて大悲を成ず。(『大智度論』)
菩薩の慈悲を社会的にひらけば、「自他不一」や「自他平等」といった倫理になる。あるいは「自他融即」や「自他一如」といった境地になる。言葉が硬いなあ。力瘤が入っているじゃないか。ここでは「遠いともだち」はすでに自他の差異として空間化(社会化)されている。だから「不一」や「平等」や「融即」や「一如」といった力ずくの言葉が必要になる。これらの言葉からは、たとえば谷川俊太郎の「ぱん」のいい匂いはしてこない。『注文の多い料理店』の「序」に流れている透明で澄んだ音色は聞こえてこない。ただ苦行僧の戒律みたいなものがイメージされるだけだ。
空間化された現実(つまり社会)のなかで、仏教的な慈悲は無限の奉仕や自己犠牲にしかならない。
慈悲とは自己を捨てて全面的に他の個的存在のために奉仕することである。それは現実の人間にとっては容易に或いは永久に実現されがたいことであるが、しかも人間の行為に対する至上の命法として実行が要請される。他の個的存在のための全面的帰投ということは、自己と社他の対立が撫無される方向においてのみ可能である。(中村元『慈悲』)
最初からできないことが説かれているという印象を受ける。「自己を捨てて全面的に他の個的存在のために奉仕する」なんて、いかにも思考の息遣いが苦しい。このできないことをやるのが、真の仏教者としての修行であり、ゆえに彼らは個我をいかにひらくかということに腐心する。厳しい修行によって「空」の境地に至る。これが仏教的な「解脱」である。
こうしたやり方を、宮沢賢治はその全作品をとおして否定していると思う。すでに見たように自伝的事実として、宮沢賢治という人は法華経という宗教的信仰へ行こうとして挫折し、挫折感の表出として詩や童話を書いたことになっている。しかし彼の作品は口ごもりながら、別のことを言おうとしているように見える。厳しい修行を経た高度な仏教者でなくても、自分のように信仰の途中で挫折し、田舎に戻って結婚もせず、親がかりで生涯を終えようとしている「デクノボー」であっても、悪人も善人も、聖人も凡夫も、誰もがみなおのずからなる慈悲の世界を生きている。そのような世界が誰の前にも「透明な風景」として広がっている。
賢治が残した作品全体を一つの喩として読めば、そういうことを表現している気がする。自伝的事実として、彼は宗教的信仰へ行こうとして行けなかった。だが、その挫折した場所で創作された詩や童話は、法華経や仏教といった信仰の世界よりも、はるかに深くて広いものを表現できていると思う。