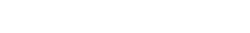第7話 遠いともだち②
大切なことは、「遠いともだち」がみんなここに、ぼくたちのなかにいるということだ。あそこではなく、ここにいる。あそこにいる、と口にした途端にともだちは変質して別のものになってしまう。それはともだちではなくなるかもしれない。下手をすると敵になり、殺したり殺されたり、食べたり食べられたりするものになる。なぜなら、「あそこ」とともに彼らは可視化されてしまうからだ。
あの日からだ。ぼくが道行く人の鼻と背丈に注目するようになったのは。市の中心部に妹のアナとお遣いに行ったときは、ふたりして、あの人はフツ、この人はツチ、とこっそりあたりをつけ、耳打ちしあったものだ。
「白いズボンをはいているあの男の人、あれはフツだよね。ちっちゃくて、鼻が平べったい」
「ああ。あそこの帽子をかぶっている人は大柄で、がりがりで、鼻がすっとしている。ツチだな」
「あっちの縞々のシャツの人は、フツで決まりね」
「まさか。よく見ろよ、のっぽで、痩せてるじゃないか」
「でも、鼻はつぶれて大きいよ!」
(ガエル・ファイユ『ちいさな国で』加藤かおり訳)
あそこではなく、ここなんだ。ここにいるんだ。そう考えなくてはならない。彼らは「遠いともだち」として、ぼくたち一人ひとりのなかにいる。誰のなかにも〔小岩井農場〕はあって、汽車に乗って寂しい町の駅で降り、とぼとぼ歩いていくうちに風景が透明になっていく。透きとおった景色のなかから、ユリアとペンペルがあらわれる。
彼らとともにあるぼくたちは、ツチ族でもフツ族でもない。日本人でも中国人でもモンロイドでもアングロサクソンでもない。たぶん男と女でもない。国籍や民族や宗教など影も形もない。そんなスケールの小さな話ではないのだ。ユリアとペンペルという「遠いともだち」の名前には、少なく見積もっても十数億年の時間が包摂されている。魚類から両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類、人類……すべての宗族を分け隔てなく包み込んだところでの「遠いともだち」だ。彼らはぼくたちのなかにいる。いつもここにいて、ともに生きている。そのようなものとして人間を、歴史をイメージしてみよう。
ここで再び糖質セイゲニスト・夏井睦さんに登場していただきます。ヒトが昆虫などを採集して暮らしていた500万年~5万年前に至る長い「先史時代」、彼らはJR山手線に囲まれる範囲に6~60人という状態で暮らしていた。一日の労働時間は2~3時間、膨大な余暇を主に性行為にあてていた、としよう。まあ、他にすることもなかっただろうしね。でも、1平方キロメートルあたり0・1~1・0人の人口密度では、相手を見つけるのも大変だったろうな、っていうか、ほとんど遭遇のチャンスはなかったのではないだろうか。仮に15人ほどの集団で生活していたとすると、ほぼ現在の一夫一婦制に近い夫婦生活であったと考えられる。『源氏物語』の時代の帝などよりは、よほど慎ましい性生活であったはずだ。
彼らの脳の基本仕様は、「努力しない、頑張らない、困ったら逃げる」であるから、まあ呑気な人たちと言ってよかろう。描き、話し、踊る、陽気な面々である。彼らは「遠いともだち」として、いつもぼくたちのなかにいて、ともに生きている。そのことを宮沢賢治は理屈以前に、生の実感として生きていたのではないだろうか。彼という一個の生は、「遠いともだち」とともにしかありえないものだった。
この詩人は花巻農学校で先生をしていたとき、生徒たちと野外実習に出ていて、突然飛び上がって「ほ、ほうっ」と叫ぶことがあったらしい。畑山博が『教師 宮沢賢治のしごと』という本のなかで、賢治の教え子たちに取材したことを書き記している。
ほほっ、ほほうというのはね、賢治先生の専売特許の感嘆詞でしたよ。どこでもかまわず、とつぜん声を出して、飛び上がるんです。
くるくる回りながら、足ばたばたさせて、はねまわりながら叫ぶんです。
喜びが湧いてくると、細胞がどうしようもなくなるのですね。身体がまるで軽くなって、もうすぐ飛んでいっちまいそうになるのですね。
たぶん賢治の傍らには、いつもユリアとペンペルがいたのだろう。描き、話し、踊る、陽気な面々とともに彼の生はあった。そんな気がする。(2017年12月15日)