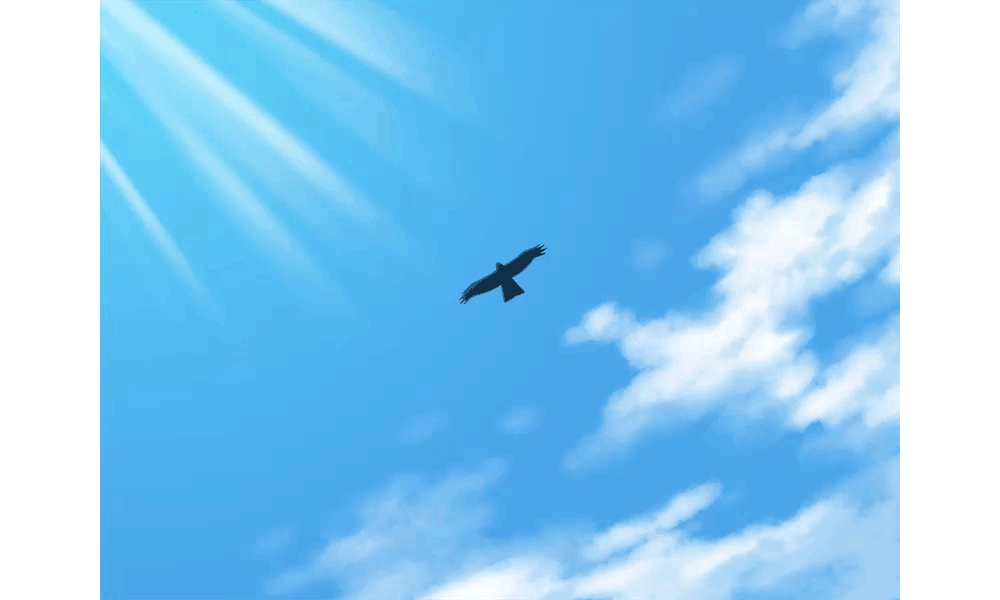少年は毎日、日が暮れると海辺に転がっている流木を集めて火を焚いた。荒波に洗われた木は、樹皮が削り取られて白い幹がむき出しになっていた。それは海に棲む巨大な生物の白骨を想わせた。漁船の燃料に使う油を、家の者に内緒で瓶に詰めて持ってきていた。細い枝を組み上げた上に油を注ぎ、マッチを擦ると簡単に火は熾った。小さな火を少しずつ太い木に移していった。
大海原に一つだけ取り残されたような島だった。陸からは遠く隔てられている。島には百人ほどが暮らしていた。小さな港があり、狭い土地に肩を寄せ合うようにして建つ家々があり、山の上の方まで畑が築かれている。畑には主に芋や麦が植えられていた。水と土地が乏しいため、水田はわずかしかない。ほとんど自給自足の島で米は貴重品だった。男たちが日常に飲む酒も、芋や麦を蒸留したものが主だった。
海を隔てて遠方に一つの島が浮かんでいた。少年が住む島から唯一見える島だ。大きさははっきりわからないが、たぶん彼の島とあまり変わらないだろう。不思議なのは、誰もその島へは行こうとしないことだった。危険な潮の流れが二つの島を隔てているかもしれない。もっと別の理由があるのだろうか。何度かたずねてみたけれど、大人たちは言葉を濁してしまい、納得のいく答えを得ることはできなかった。遠くに見える島は、少年には生きてたどり着くことのできないところに思えた。
夜になると、海を隔てた島の集落にもほのかな明かりが灯る。家々の明かりは、小さく瞬きしているように見えた。灯火の下に、自分と同じくらいの歳の少女が暮らしている。いつのころからか彼は、そんなことを考えるようになっていた。彼女もまた毎日、この島を眺めている。そして島に住む少年のことを想っている。来る日も来る日も海岸で焚火をしながら、海の向こうの離れ小島を見ているうちに、それは彼のなかで確信に近いものになり、一人の少女が実体を帯びてきた。
おそらく行こうと思えば行けないことはない。だが生きてたどり着くことは難しい。そんな島に一人の少女が住んでいて、彼と心を通い合わせている。少女を想うことで、彼は未知の自分を発見した気がした。自分だけでは知りえなかった幸せ、悲しみ、不安、言葉にできない感覚、感情、衝動……。
漁にはいつも一人で出た。朝、港を出て夕方に帰ってくる。翌日に水揚げして、その日は漁具の手入れをしたり、氷を積んだりして準備をする。つぎの日、また漁に出る。その繰り返しだった。一年のうちに半分くらいは海の上にいる計算になる。
漁は遊び半分で父親に付いていくうちに自然とおぼえた。長い糸にたくさんの針を付けて獲物を狙う漁法は、父の代から定着したものらしい。およそ二百本の針には漁場へ向かう途中で餌を付ける。船を走らせながらそれを降ろしていく。五分ほどで千メートルの糸を降ろし終える。半時間から四十分ほどして引き揚げる。こちらは小一時間かかる。同じことを一日に六回、七回と繰り返す。
父と一緒に漁に出ていたころは、針を降ろしてから一時間くらい待つのが普通だった。たくさんの針に獲物がかかっていたので、待つ甲斐もあった。いまは一匹もかかっていないことがある。魚の種類も小粒になっている。だから短い時間で揚げて、糸を張る回数を増やさなければならない。近くで魚が獲れなくなったので、遠くまで船を走らせる。そのための装備も必要になる。燃料も高くなっている。経費に追われて、いくら水揚げしても間に合わない。
浜に打ち上げられた死体を、彼は子どものころから幾度となく見たことがあった。父親と一緒に海に浮かんでいる死体を引き揚げたこともある。海で死んだ者の皮膚は濡れた障子紙のように身体から剝がれそうになっていたり、身体が二倍くらいに膨張していたり、その両方だったりした。顔がほとんど蟹に食べられている死体を見たこともある。蟹は肉の柔らかいところから食べるので、とりわけ目や口のまわりの破損がひどかった。海で出会った死体は、下半身をほとんど魚に食べられていた。海で死んだ男たちは、見るも無残な姿で家族と対面することが多い。
高校生のときに父親が亡くなった。海で行方不明になったまま見つからなかった。無残な姿での対面は免れたものの、これはこれで面倒なことだった。まず法律上、一年は死亡とみなされない。家族のほうでも、死んだことを認めたくない気持ちがあって、なかなか葬式を出せない。そのあいだも誰かが漁に出なければならない。彼は卒業を目前にして島に戻ってきた。漁師に学歴は関係ない。高校くらいは出ておけと言った父親もいなくなった。
島では変わり者と思われていた。時化で誰も船を出そうとしないときも、彼だけは漁に出たからだ。しかも獲物を求めて遠くまで行く。時化で水揚げが少ないと、当然値もいい。家には病気がちの母親と中学生の妹がいた。五つ下の弟は、彼が中退した街の高校に通っている。あと一年ほどは面倒を見なければならない。そろそろ嫁をもらう歳になっていた。世話をしようという人もいたけれど、本人にはその気がなかった。
いまの暮らしが向いていると思っていた。波と魚を相手にする毎日。長い時間を海の上で過ごしているうちに、彼は無口になった。一人でいることを苦痛に感じなくなった。いつのまにか人間も物も、あまり好きではなくなっていた。
海辺を旋回する鳶にも、もっと低いところを飛びまわるカモメにも、波打ち際に横たわるその動物が死んでいるのか生きているのかわからなかっただろう。本人にもわからなかったくらいだ。
最初に感じたのは痛みだった。身体中が焼けるように痛かった。強い日差しを浴びて、むき出しの皮膚は海岸に転がる石ころと同じくらい熱くなっている。反射的に顔に手をやった。幸い蟹に喰われてはいないようだ。皮膚はちゃんと肉にくっついているし、身体が水を吸って風船のように膨らんでもいない。どうやら生きているらしい。安堵とともに、溶解するような疲労に襲われて彼は意識を失った。
果てしない闇のなかを漂っている気がした。海岸で感じたような痛みはなかったが、そのぶん自分が生きているという確信ももてなかった。いまのところ生と死の潮目を漂っているらしいが、どちらかというと死に向かって流されている気がした。生から遠ざかる離岸流にとらわれてしまったのかもしれない。
目が覚めると見知らぬ部屋にいた。額に入れて鴨居に掛けてある何枚かの古い写真が目に入った。この家に暮らした者たちの遺影だろうか。
「気が付いたか」
部屋の隅に女がいた。
「もう大丈夫じゃよ。怪我はしとらん。肺にちょっと水が入っとるようやけどね」
その声を聞き、自分と同じ年恰好の相手を見たとき、彼は激しい咽喉の渇きをおぼえた。
「水を……水をくれんか」
「お水か。いま持ってくるけんね」
女は部屋を出ていった。その後ろ姿を追いながら、彼は懐かしい気持ちになった。海岸で焚火をしていた少年の日のことを思い出した。あのとき想っていた少女。彼の心のなかで実体化し、実在するに至った一人の少女が、十年のときを隔てていまここにいる。だが不意に虚しさをおぼえた。なんと言えばいい? 通じるわけがない。肺に水が入って頭まで変になったと思われるのが落ちだ。
女に世話をされて、体力は少しずつ回復していった。目覚めているあいだはずっと女のことを考えていた。眠っているあいだも、考えつづけていたような気がした。数日後には起き上がれるようになり、さらに屋外にも出られるようになった。家の裏は石垣を隔ててすぐ海になっていた。潮が満ちてくると、波のある日には石垣に当たって水しぶきを飛ばす。
「海が荒れた日は水が家のなかまで入ってきて大変なんよ」
「どうしてそんな近くに家を建てたのかの」彼がおかしそうに言うと、
「昔は潮が満ちてきても、家の裏には白に砂浜が残っとった」女は真顔で説明をはじめた。「村の人らはそこを通って行き来できたし、石垣も必要なかったわけやね。うちが生まれたころに西の波止ができて、それで潮の流れが変わったんよ。少しずつ砂が削られて、いまみたいになってしもうた。波止ができたのはええけど、こんなことになるとは誰も思うてなかったんやろうね」
その石垣の修理を手伝うことになった。女の父親は寡黙な男だった。彼が家に厄介になっていることに嫌な顔をしないかわりに、親しげに言葉をかけてくることもない。家の裏の石垣は粗末なものだった。近くの磯から石を拾ってきて築いたものらしい。石工でも雇って丈夫な石垣を造ればいいにと思ったが、口には出さなかった。
暮らしが貧しいのは彼のところと同じだ。平地が少ないので山の斜面に段畑を築いて芋や麦などを作っていた。畑は山の奥まで拓かれている。彼の島でには養っていけない子どもは間引きされたという言い伝えが残り、水子供養の地蔵があちこちに立っていた。同じ地蔵がこの島でも見られた。
「わしらは間引かれずに生き残ったわけだな」冗談めかして言うと、
「馬鹿やね」女は呆れた口調で答えた。「そんなのは大昔のことよ。お地蔵さんの後ろに字が彫ってある。消えかかって見えにくいけど、江戸時代の年号らしいよ」
彼女の家の畑は山の中腹の見晴らしのいいところにあった。途中で広々とした草地の脇を通る。草は短く刈られ、村の人たちによって大切に管理されているらしい。
「もったいないの、こんな広い土地を。畑にでもすればええのに」
「お墓を畑にはできん」女は事も無げに言った。
彼ははっと胸を衝かれて足を止めた。何も考えられなくなり、しばらく草地を眺めていた。
「この島で亡くなった人はみんなここに埋められるんよ」女は言うまでもないことを付け加えた。
いつのころからか察していたのではなかったか。大人たちが島へ行くことを避けるのは、この島の人たちが代々受け継いでいるしきたりのせいであること。死んだ者は焼かねばならない。彼の島ではそう考えられていた。現に死者たちは寺の裏の丘で火葬にされた。野天に穴を掘り、周囲を煉瓦で囲っただけの簡単なものだったが、村で死んだ者はそこで荼毘に付された。穴のなかへ棺桶を降ろし、割き木と麦わらで焼き上げる。これを怠ると疫病が流行ると信じられていた。だからなおのこと、島の者たちは土葬の習慣を守りつづける者たちを忌諱していた。
「おまえもここに埋められるのか」
「そうなるやろうね」女は遠い目をして答えた。「いつのことかわからんけど」
土のなかで腐っていく女の姿がちらりと頭をかすめた。やがて彼女は振り向き、目を合わせたけれど、感情を読み取ることはできなかった。
「おれの島に来ないか」譫言のように言った。
「うちはこの島でしか暮らせん」女は悲しそうに答えた。
「どうして」
「昔からそうやったから」諦めたような言い方だった。「島の女は島の男と結婚する。そして死ぬまで島で暮らす」
「そしてここに埋められるのか」
女は答えなかった。彼もそれ以上は言葉を思いつかなかった。長く海の上で暮らしてきたせいだ。
「島を出たくないのか」ようやく口にすると、
「きまりやけん」女は表情のない声で答えて歩きはじめた。
まだ二人が子どものころに、両家の親たちがきめたことらしい。許嫁の家で世話になっている彼に、男は悪感情をあらわさなかった。何度か漁具の手入れを手伝った。長い時間、二人は黙って作業をつづけた。話すべきことがあるはずだ、と彼は思った。この男にも、おれにも。わかっているのだろう? おれたちには話すべきことがある。だが彼自身、自分が考えたり感じたりしていることを口にするのは苦手だった。この男もそうなのかもしれない。おれたちは似ているのだろうか。認めたくないことだが。
ある日、二人は漁に出た。男が漁場に船を駆るあいだ、彼は針に餌をつけた。漁法まで同じだった。この男も同じやり方で魚を獲りつづけてきたのだ。まるでもう一人の自分がいるみたいだった。むしろこちらが現実で、かつての島の暮らしのほうが夢か幻のようにも思えた。
「子どもが生まれたら、漁師にはさせるまいと考えとる」引き揚げるのを待つあいだに、男はそんなことを言った。「ここらの漁業は先が見えとる。わしらの代で終わりじゃ。男の子やったら街の学校にやって給料取りにする」
彼は男の死を願った。顔を蟹に喰われるような無残な死は望まないまでも、父親と同じように海で行方不明になってくれたらいいと思った。この男の場所にはおれがいるはずだったのだから。
「女やったら?」
男はしばらく思案する素振りを見せた。
「やっぱり街の学校にやって給料取りと結婚させるやろうな」
屈託なく笑う男を、彼は憎いと思った。その一方で、憎み切れないとも感じていた。この男を憎むことは、彼女を憎むことにもなる気がした。
「そろそろ揚げるか」
糸を手繰る男の様子を横目で見ながら、彼は心を決めた。一日も早く島を出よう。おれはこの男を殺した。少なくとも心のなかで一度は殺したのだ。おれの心には男の血がついている。一生、洗い落とすことのできない血が。
女の家で夜を過ごすことが、いまさらながら辛い苦行のように思えた。彼女には許婚がいる。これから先、数え切れぬ夜を同じ布団で寝るのはあの男だ。悪いやつではない。まっすぐな海の男のようだ。知らない者同士として海の上で出会ったら、手を貸し合うような仲になれたかもしれない。彼女はその男のものだ。入り込む余地はない。
一方で、なぜ自分ではなかったのかという不条理な思いを払いのけることができなかった。来る日も来る日も海岸で焚火をしながら、彼女を想いつづけていた自分が、あの男の場所にいないのはなぜなのか? 本来の相手はおれだったはずではないか。おれたちは一緒に大きくなってきた。毎日、毎時間、ともに生きてきた。何かの手違いで入れ替わってしまったのだ。おれとあの男が。そうでなければ彼女のほうが間違った島に生まれたのだ。どっちにしても男一人が余分だった。
男が彼を島に送り届けてくれることになった。女の許婚の船で元の場所へ送り届けられることが、彼を皮肉で自嘲的な気持ちにさせた。体よく厄介払いされるようではないか。それでいいのかもしれない。いまはただ一刻も早く彼女から離れたかった。これ以上一緒にいることはできない。彼女といると胸が苦しくなる。追い詰められたような、いたたまれない気持ちになる。
それでも最後にもう一度、女と二人きりになりたかった。夕暮れどき、家の裏の干潟に女を誘った。潮は遠くまで引き、干潟は沖まで現れていた。
「ここらの砂には貝がたくさんおるんよ」
彼は足下に目をやったまま黙って頷いた。
「いよいよ明日、帰ってしまうんやね」
ありったけの燃料を積んで、どこまでも船を進めれば見つかるのではないか。この期に及んで、彼はまだそんなことを考えていた。おれは自分の島と、この島のことしか知らない。あとは高校時代に数年を過ごした街くらいのものだ。どこかにあるのではないか。きっとあるはずだ。おれたちが二人で生きていける場所が。そのとき彼は、少年時代に自分がこう考えたことを思い出した。少女の暮らす島は遥かに遠い。生きてたどり着けないほど遠い島なのだ。
「ここにいたことをおぼえておこう」歩きながら彼は誰にともなく言った。「この干潟、家の裏の石垣、裏山の段畑、死者を埋葬するために草原……」
「うちは?」女は悪戯っぽくたずねた。
足は止めなかった。立ち止まれば抱き寄せたくなる。温かい顔に顔を近づけ、唇を押し当てたくなる。女の熱い息を吸い、塩の味がする舌に触れたくなる。そして自分の気持ちを告げたくなる。それは引き返すことのできない過ちのように思えた。
みんな二人のもので、これから永遠に二人のものだ。おれたちはもともと一つのものだった。離れているのは仮の姿に過ぎない。そうではないのか?
「海で死んだら、骨は笛にしてもらおう」
「縁起でもないことを言うもんやないよ」女は真顔でたしなめた。
「もしものことだよ」
これから何をしても、どんな人生を送っても、このひとときに勝るものは得られないだろう。同じようなことは二度とは起こらない。おまえと別れれば、悲しみは永遠に残る。永遠に残る悲しみを抱えて生きていくためには、心を麻痺させるしかない。何も感じない心とともに生きていくしかない。そんな寂しい心のなかに、一つくらい希望をもってもいいだろう?
「本で読んだことがある」彼は遠い記憶を手繰るように言った。「高校の図書館で手に取った本に、そんなことが書いてあった。チベットあたりでは、人間の骨で笛を作るらしい」
「気持ち悪いな」
おれの骨笛をおまえに届けたい。晴れた日に、島の見える丘の上でおまえがおれを吹く。おまえの息がおれのなかに入ってくる。するとおれは鳥になって、おまえのもとへ飛んでいこう。