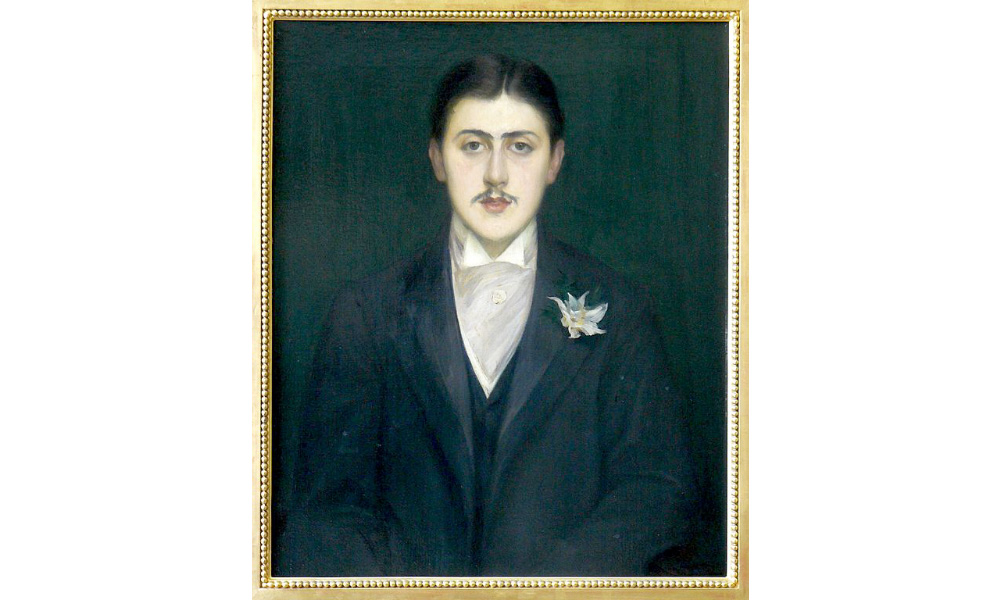1.福岡で小説を書くこと
大学進学のためにこちらに来て、以来40年以上ずっと福岡に住んでいます。どうして福岡で小説を書いているのですか、上京しようと思ったことはないのですか、とたずねられることがあります。どうしてと言われても、結婚して子どもが生まれ、その子どもが学校に通うようになって、というふうにして根付いちゃったわけですね。
いまはインターネットなどが発達して、地方で小説を書くことのハンディはほとんどなくなりましたが、当時は上京して文壇や編集者に顔を売らなきゃダメだといった助言をしてくれる先輩作家の人たちがいました。つまり営業をしろということですね。好意で言ってくれているのですが、こっちは「大きなお世話だ」と思っていました。ぼくがドストエフスキー級の作品を書けば、ここが世界文学の中心になるにきまっているじゃないか、などと生意気なことを言って顰蹙を買っていました。半分は冗談ですが、半分は本気でそう思っているところがあって、やっぱり自分が言葉を紡いでいるところが世界の中心だと思っています。文壇の付き合いなんかしなくてよかったと、いまは本心からそう思っています。
もう一つ、福岡で書いていてよかったと思うのは、文学以外の仕事をせずに済んだことです。東京なら雑誌関係の仕事など、出版社の周辺で何かしら食い扶持を得るための仕事があると思うんです。小説家を志していたのに、いつのまにかそっちが本業になったという人もいるでしょう。ぼくが若かったころは、福岡でそういうサイドビジネス的な仕事を探すのは難しかったのです。せいぜい塾の先生か家庭教師、予備校の講師くらいでした。結果的に、書くという作業を、小説や批評といった自分がやりたいことだけに向けることができた。それはいま振り返るとよかったと思います。そのぶん奥さんや家族には苦労をかけましたけどね。
2.なぜ書きつづけているのか
ぼくはいま九州産業大学というところで授業を受け持っているのですが、そのときに学生さんから、小説のテーマやアイデアをどうやって思いつくのか、といった質問をよく受けます。この質問に答えようとすると、なぜ小説を書いているのかという話になります。なぜ書いているのか、書きつづけているのか? 答えは簡単で、面白いからです。小説を書いているときがいちばん充実感がある。たまにだけれど小さな達成感もある。つまり考えることを含めて書くことは、ぼくにとっていちばんやりがいがあり、自分が何かしているという実感を得られるものなのです。
だから書くことを「仕事」と思ったことはありません。ただ好きなことを一生懸命にやってきたという感じです。いまだに創作に職業意識が伴わない。そもそも小説は仕事になりません。ほとんどの場合、収入に結びつかないからです。学生さんたちにも、書くことを職業として考えないほうがいいと言っています。お金を得ようとすると、かえって自分を追い詰めることにもなる。書きたいものを書きたいように書くのが小説です。いまはブログでもなんでもあるのだから、そういうところに作品を発表すればいい。数は少なくても読んでくれる人はきっといるはずです。
ぼくの場合は、たまたま本が売れたおかげで生活できているけれど、それは偶然で、当人が意図したことではありませんでした。小説で食べていこうと思ったことは一度もありません。家族や周囲の人たちに支えられて、なんとか40年近く小説を書きつづけてこられたということです。そうして振り返ってみて、やっぱりこれが自分にとっていちばんいい生き方という気がします。
3.テーマは自分。
すると小説のテーマはおのずと「自分」ということになります。なぜなら書いたり考えたりすることは、自分が生きていることそのものだからです。この自分が生きていることのなかに、あらゆる題材が含まれている。あとはそれをいかに書くかです。
こんなふうに考えると、小説を書くことは脳機能よりも免疫機能に似ているかもしれません。免疫というと異物を排除する、というふうに思われがちですが、ほんとうはそうではなくて、免疫系のまなざしは自己に向けられているのだそうです。この自己がウイルスに侵入されるなどして非自己化すると、免疫反応が起こって、非自己化した自己を攻撃して排除してしまうというわけです。
小説のまなざしもこれと似ています。見つめているのは自己です。自分のなかに起こる変化、非自己化に微妙に反応して言葉を発する。これが文学というシステムだと思います。ぼくたちは毎日を生きていくなかで常に変容し、多様化していきます。こうした変化をみつめているのが文学のまなざしです。そこが政治経済のまなざしとも自然科学のまなざしとも違う、文学の特徴的なところです。
ぼくたちの自己はさまざまな契機、無数の原因によって変化していきます。たとえば社会に出て仕事をすることで変わっていく。人と出会うことや、病気になることでも変わっていく。こうして見ると、自分や自己は確固とした固定的なものではなく、人か事象かを問わず、大小の出会いによって常に変化しつづける、流動的かつ行動的なものと言えるでしょう。
このように変化しつづける自己をみつめる、もう一つのまなざしをもつことは、生きていることを楽にしてくれると思います。たとえば病気になったとき、病んでいる自分を見守るもう一人の自分をもつことは、病むという状態にある者を楽にしてくれます。ぼくなどは夫婦喧嘩をしながら、これをうまく小説に使えないかな、などと思っていることがあります。そう思ったときには、もうその場から離れている。現場から身を引いて、喧嘩をしている自分とのあいだに少し距離ができます。日常的に小説を書いていると、このような距離をつくり出すことが癖になって、息遣いを少し楽にしてくれている気がします。
4.フィクションの可能性
ところでぼくたちは、どうして小説という面倒なものを書こうとするのでしょう。自分をみつめ、自分について書くだけなら、小説でなくてもいいはずです。たとえば日記や自分史みたいなものでもいいかもしれない。カフカの日記はそのままで充分に面白いものですが、日記だけでは済まなかったから、『変身』などのフィクションを書いたのでしょう。このように小説やフィクションでないと片付かない問題が、やはりあるような気がします。
ぼくは『世界の中心で、愛をさけぶ』をはじめとして、いわゆる恋愛小説と呼ばれるものを幾つも書いてきました。『世界の中心で』みたいあからさまではないけれど、誰かを好きになるとか、決定的な出会いを果たすといったことを、いまだに書いているわけです。ぼくも60歳になり、もう少し年相応のことを書いたほうがいいのかもしれませんが、あいかわらず青臭いことを書いています。
なぜ還暦を迎えたおやじが恋愛小説じみたものを書きつづけているのか。これには自分なりの理由があります。それは恋愛としてあらわれる情動が、人間のなかにある最善にして、最上のものだと確信しているからです。無暗に誰かを好きになって、その人と結婚して家族をなす。できれば子どもをつくって、その子どもとともに自分も成長していく。これ以上に善きもの、悦ばしいものが、人の一生のなかにあるとは思えません。この善きもの、悦ばしきものの根源には、それまで見ず知らずだった赤の他人を、一瞬にして自分以上に好きになってしまうという摩訶不思議な情動があるのです。この不思議な心映えが、ヒトを人間にしたとぼくは思っています。これがあるかぎり、テロと戦乱にまみれながらも、人類はまだしばらくは滅びずにやっていけるのではないでしょうか
考えても見てください。トランプの息子と習近平の娘が、飛鳥みたいな豪華客船の上で出会う。ラウンジかレストランで「ハーイ」とか言って仲良くなってしまう。ありないことではありません。国籍の違う男性なり女性なりを一目見たときから好きになってしまうことは、誰の身にも起こり得ます。そうして仲良くなった二人が、「おとうさん、わたしたち結婚します」と言えば、その瞬間からトランプと習近平は親戚になってしまいます。自分の娘や息子、孫たちが暮らす国をミサイルや核兵器で攻撃しようと思うでしょうか? 北朝鮮だって建前は専守防衛です。どの国も自国の安全のために武器を持つ、自己防衛のためにどんどん軍備を過剰にしていく。「おとうさん、わたしたち結婚します」に勝る安全保障はありません。人を好きになるという情動は、いかなる軍事力をも凌ぐのです。
この善きものを、言葉でしっかりとらえたい。そのために小説というフィクションを書く必要があるのです。現実にぼくたちが体験する恋愛は、いわば瞬間芸のようなもので、ぱっと燃え上がって過ぎてしまいます。定着しないし持続しない。人間のなかにある至上のもの、この上なく善きものがあらわれても、それは一瞬のうちに過ぎて、あとは日常の反復のなかで見えなくなってしまう。これを言葉として確かなものにするために、小説というフィクションが必要だと思うのです。
こういうふうに自分のやりたいこと、書きたいことが見えてくるのは、ある程度の年齢になってからだと思います。歳をとって、いろいろなことを体験するなかで少しずつわかってくる。『世界の中心で』を書いたのは30代の終わりですが、それから20年ほど経って、あのころよりも理解が深まっていることはたくさんあります。読者に受け入れられるかどうかは別として、自分のなかではやりがいのあることだと思っています。
5.長く生きつづける言葉
ここで少し恋愛から離れて、別の話をしましょう。長い年月を経て生き残っている言葉があります。たとえば『聖書』や『コーラン』、日本でいえば親鸞の『歎異抄』などがそうでしょうか。長く生きつづける言葉とはどういうものでしょう? ここではシンプルに、「人を元気づける言葉」と考えてみます。生きる力を与えてくれる言葉ですね。『聖書』の言葉は2000年にわたって人々を元気づけ、生きる力を与えつづけてきました。フランス革命の「自由・平等・友愛」もそうです。この高邁な理想を実現するために、200年の及ぶヨーロッパの近代はあったと言ってもいいくらいです。
しかし時代は移り、状況は変わりました。いま「神」という言葉を口にすると、ただちに殺し合いがはじまります。「神」が超越的な観念であることが原因だと思います。ローカルな圏域だけなら大きな問題はなかった。しかしグローバル化によって相互の交流が起こるようになると、「ゴッド」と「アッラー」のように超越性Aと超越性Bがそこかしこで衝突するようになる。それぞれが超越的だから相手の超越性が認められない、というふうにして「神」という言葉は行き詰まっていると思います。
人権思想も同じです。イスラエルがパレスチナにたいしてやっているようなことが、現在の自由・平等、それに友愛の姿です。同胞の自由を守るために敵を監視する。何か不穏な動きがあれば再起不能なまでに痛めつける。もともと「自由・平等・友愛」が通用するのは一つの国家の内部だけです。人権は「国民」というフィクションを前提にしないと成り立たちません。この虚構が内からも外からも決壊しつつある。イギリスのEU離脱もヨーロッパの移民・難民問題もアメリカや日本で顕著に見られる中間層の没落も、大枠ではそのようにとらえることができるでしょう。
2000年にわたり人々を元気づけてきた「神」も、200年にわたり人々に生きる力を与えてきた「自由・平等・友愛」も、いまや賞味期限が切れつつあります。「神」や「自由・平等・友愛」にかわる新しい言葉、この先の何百年か人間を元気づけ、うずくまっている人に生きる力を与える言葉をつくる必要があります。
6.言葉が届くということ
では「人を元気づける言葉」とは、どのようなものでしょう? 現在の日本の社会を考えてみましょう。ぼくたちのまわりでいちばん元気がないのは、たとえば末期の癌を宣告された人たちです。彼らに届く言葉はあるでしょうか? 難しい問題です。しかし、この難しい問題をクリアしないかぎり、文学は本懐を遂げないとぼくは思っています。
医者から「あなたは癌です。余命一年です」と言われる。その瞬間から、どんな言葉もその人には届かなくなります。唯一届くのは治療の言葉、さらに言えば主治医の言葉だけです。これほどまでにぼくたちの言葉は無力なのです。「あなたは癌です」という医者の一言にまさる言葉を、ぼくも含めて、この国で文学にたずさわる者の誰一人としてつくることができていません。
病気や治療の言葉だけに覆いつくされた生はあまりにも苦しいと思います。孤独で心細いはずです。だから余計に医学を頼ってしまうのかもしれません。言葉が届かないことは、何よりもぼくたちを無力にします。もちろん主治医の言葉も大切でしょうが、それ以外にもいろんな言葉が届けばいいと思います。そうすれば同じ闘病生活でもずいぶん楽になるはずです。
具体的に考えてみましょう。死を受け入れることができずに苦しんでいる人がいるとします。彼や彼女にたいして、ぼくたちはどんな言葉を届けることができるでしょう? どんな言葉なら届くでしょうか? そもそもそうした状況で届く言葉はあるのでしょうか? キリスト教を信仰している人には『聖書』の言葉は届くかもしれません。日本人の場合であれば、禅語や通俗化した親鸞の言葉などはいくらか届いているのでしょうか。いずれも長い年月を生き延びてきた言葉の力だろうと思います。しかし本当に必要なのは、いまの時代を生きているぼくたちが発しうる言葉です。
自分の大切な人が死を迎えようとしている。その人はぼくの連れ合いかもしれない。子どもかもしれない。いずれにしても大切な人です。その人に届く言葉は既成の宗教の言葉などではないでしょう。その人のことを誰よりも大切に思っている一人ひとりの、心づくしの、手作りの言葉であるはずです。それはどういう言葉でしょう? おそらく言葉を発する者に本当に届く言葉だと思います。大切な人が苦しんでいる。大切な人だから、その人を見ている自分も苦しい。そんな自分に届く言葉があれば、その言葉は相手にも届くような気がします。彼(または彼女)の死を受け止め、受け入れることができる言葉を、自分にたいしてつくることができれば、それは死んでいく彼や彼女にも届くのではないでしょうか。
逆の場合を考えてみます。ぼくが末期の癌か何かで死を迎えようとしている。それを心の底から悲しんでくれる人がいるとします。あとに遺される相手の悲しみや苦しみがやわらぐ言葉を、ぼくがその人のためにつくることができれば、その言葉はぼくにも届いていると思います。こんなふうに考えていくと、言葉の本質は「ふたり」であると思えてならないのです。「ふたり」という場所で紡がれる言葉が、本当に苦しいときに、ぼくたちを窮地から救ってくれるのではないでしょうか。
7.死はどこでひらかれるか?
映画『タイタニック』を別れの場面を例にもう少し考えてみましょう。冷たい氷の海に浸かった主人公ジャックが、最愛の人であるローズに向かって「きみは生きろ」と言い残すシーンです。この短い言葉は、あの瞬間、たしかにローズに届いたと思います。だから彼女は、その後の長い人生をジャックとともに生きることができた。彼女が別の男性を好きになって、結婚して幸せな家庭をつくり……といったこととは一切関係なく、彼女はおばあちゃんになるまでずっとジャックと一緒だったと思います。
もう一つ。ローズに向かって発せられた「きみは生きろ」という言葉は、同時にジャックにも届いています。最期のときを迎えて、彼は最愛の人に言葉を届けることができた。言葉自体は「きみは生きろ」というありきたりなものですが、その言葉は彼自身にも届いて、現実として生きることのかなわなかった何十年かを、一瞬の永遠として彼に生きさせたように思います。あのとき二人のあいだに死はありませんでした。死がもたらす虚無や絶望や孤独はなかったと思います。「きみは生きろ」というたった一つの言葉によって、死を消すことができている。
言葉が届くとは、そういうことだと思います。たった一人の大切な人に言葉を届けるとき、その言葉は自分にも届く。そうして「あなた」と「わたし」が隙間なく重なる。ここで死は超えられます。もう一つ、ぼくの好きな別れの場面を紹介しましょう。
ぼくがじっと手を握っていると、祖父の顔に笑が広がった。「今生も悪くはなかったよ、リトル・ト リー。次に生まれてくるときは、もっといいじゃろ。また会おうな」そして、祖父は吸い込まれるように急速に遠くへ去っていった。(フォレスト・カーター『リトル・トリー』)
白人によって強制移住させられたチェロキー族の末裔でもある祖父が、孫のリトル・トリーに別れを告げる場面です。おじいちゃんの言葉はたしかにリトル・トリーに届いていると感じられます。同時に、その言葉は祖父自身に届いている。手作りの心づくしの言葉によって、祖父と孫が隙間なく重なる。そこで死は超えられている。一人で死をひらくことはできません。死は「ふたり」という場所でだけひらかれる。そうした「ふたり」の場所で紡がれる言葉を、ぼくは「文学」と呼びたいと思います。(2019.5.26 福岡市総合図書館)