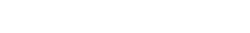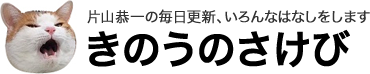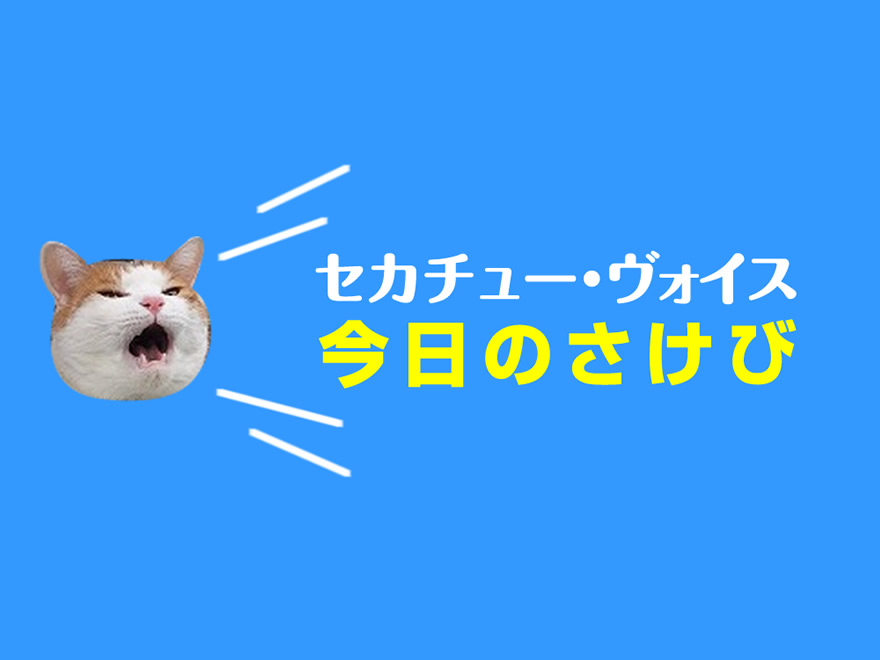古代の信仰の多くが、超自然的なシンボルや超越的存在を必要としたのは、人智を超えた強大な力によらなければ、自分たちのなかに潜在している激烈な衝動、そこから噴き出してくる狂乱と錯乱の野放図な奔流を、抑圧しきれないと考えられたからだろう。人々はその前に跪き、頭を垂れて供物を捧げることで、恐怖を鎮める術を見出した。やがて原始キリスト教や原始仏教が生まれ、現世の聖人君子たちのもとで、絶えず自分たちのなかに眠っている獣性を意識し、飼いならすようになった。そうして各々の風土や気風に応じた「文明」を築き上げてきた。
だが世界中のあちこちで見られる犠牲や刑罰には、しばしば人間のなかに眠っている獣性が顔を出していないだろうか。動物でも人でも、犠牲にささげられるものたちは二つ割きにされ、肉を削がれ、骨を露わにされる。百刻みのような残酷刑にも、人間のなかに眠っているサディスティックな嗜好があらわれている気がする。こうした振る舞いは、人間のなかの動物性から生まれてくるわけではない。動物性それ自体は自然であってなんの問題もない。
人間のなかに眠っている獣性とは、太古の時代にヒトが自然から分かたれたときに刻まれた傷なのだ。ヒトが自然から引き離されたときに生じた深い亀裂と言ってもいい。この亀裂や空隙を、人間以外の動物たちは知らない。彼らは自然そのもの、それ自体であるからだ。自然から分かたれた人間だけにもたらされた恐怖と戦慄の体験。それはわれわれが想像する以上にすさまじいものだったに違いない。
ジョゼフ・コンラッドの小説のなかで、象牙を得るためにコンゴ河を遡り、原住民たちの上に絶大な権力者として君臨する男が、死の間際に口にした言葉は「恐怖」だった。「地獄だ! 地獄だ!」。これこそヒトが自然と分かたれた場所まで遡ってしまった現代人が、ほとんど無意識のうちに発したうめきではなかっただろうか。 血なまぐさい獣性は、高度な消費社会で暮らす者たちのなかにも眠っている。誰のなかにも善悪の彼岸がある。民主的な国家や共同体の外には、いまでも身の凍る恐怖と戦慄の世界が広がっている。何かのきっかけで文明の薄い皮膜が破れれば、そこは容易に血と内臓の饗宴の場になる。紛争の現場でなされる残虐非道は、その顕著な例ではないだろうか。娯楽として提供されるミステリー小説のなかで起こる猟奇的な事件もまた。(2025.8.11)