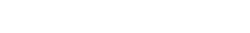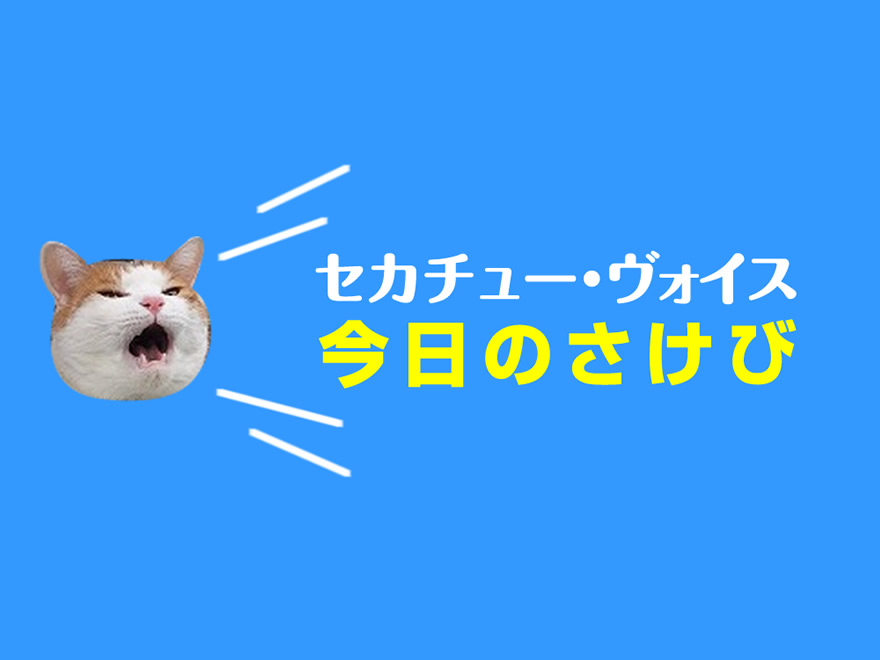人類史的普遍として人が霊や魂の観念を手放すことがなかった、そのようなかたちで過ぎない死者を身近に感じつづけてきたのは、人間のなかに「自己の手前」と呼ぶべき領域があるからだと思う。ぼくの直観では、どうもそういう気がする。
この言葉を創案された森崎茂さんからいただいメールに、「自己の手前」という言葉は「ナイーブで悩ましい」とあった。「手前があるなら向こうがあるという具合に手前はすでにというかすぐに空間化されます。同一性の手前という概念にはいつもこのきわどさがついて回る。抜きがたい思考の慣性が『手前』にもついてまわります。」
たしかに「手前」と言った途端、ぼくたちは空間化された「手前」をイメージしてしまう。「手前」は空間的な、あるいは時間的な一つの「場所」になってしまう。「場所」は科学的な粗視化の対象として計測され、計測(検出)されないものは「ない」ことにされる。こうして科学は霊や魂を否定するのだが、いかに科学的な否定圧を受けてつづけても、ぼくたちはなお死者を霊や魂と結びつけて考える習慣と縁を切ることができない。それは数量化される科学的な実体よりも、かたちのない霊や魂のほうが人間的な真実に近いからだろう。この人間的な真実を、「自己の手前」という言葉で言ってみたいのだ。
しかし森崎さんのメールにあったように、この言葉はじつに「ナイーブで悩ましい」のである。どう言えばいいだろう? ぼくが「手前」という言葉で表象したいのは、たとえば「実勢化しない」ということかもしれない。実勢化しないから「手前」なのだろう。実勢化するものは値段がついて売買や取引や交換の対象となり、経済圏に取り込まれてしまう。それにたいして「手前」は、けっして現金化されない仮想通貨みたいなものである。現金化された途端に価値を失う。不条理な価値が人間のなかにはあって、それをぼくは「自己の手前」と呼んでみたいのだ。
見方によっては不条理だけれど、それは交換価値として不条理なのであって、交換を前提としない、たとえば贈与だけで成り立っている世界を考えてみれば、あながち不条理とは言えない。ぼくたちが「霊」や「魂」と呼びならわしているものを、「自己の手前」をトークン化したものと考えてみよう。年老いて逝く親が、あるいは幼くして亡くなる子が、残される者に「霊」や「魂」というトークンを贈与してくれる。それは一般的な流通過程のなかで現金化して「いくら」と値段をつけることはできないけれど、受け取ったその人のなかでは、やわらかでやさしい温かみを湛えた至上のものでありつづけるだろう。
そうした贈与を、ぼくたちは無数に受け取って生きているのではないだろうか。そして知らないうちに、自分も誰かに何かを贈与しているかもしれない。「自己の手前」という言葉を介して、暴力の影のない、善だけで成り立つ世界に、少しずつ近づいていくことができる気がする。(2019.8.16)