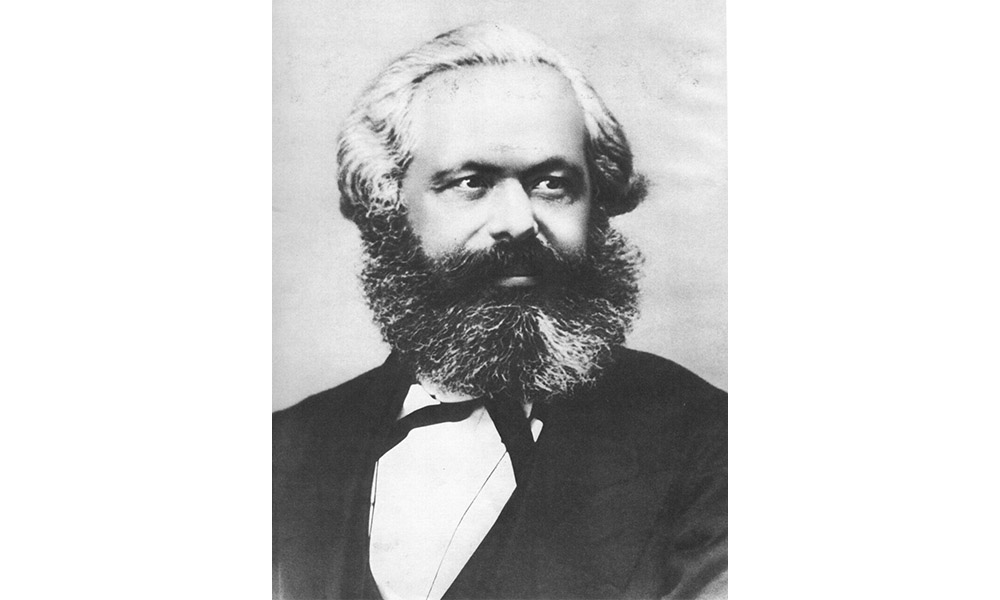1 格差の現在
国際援助団体オックスファム・インターナショナルは18日、スイスのダボスで開催される世界経済フォーラム(ダボス会議)を前に、世界の経済格差にかんする報告書を公表した。それによると2015年、世界のもっとも豊かな1%の人たちが保有する資産が残り99%の人の資産を上回り、62人の富豪の資産が世界の最貧層50%(約36億人分)の資産と同じになったそうです。ちなみに2010年には最貧層50%の資産は388人の富豪の資産に相当していたそうなので、富の集中と経済格差はますます進んでいることになりますね。(2016年1月20日付『赤旗新聞』より)
2 トマ・ピケティが証明したこと。
r>g
「r」は資本収益率で、「g」は経済成長率をさす。ピケティ氏は15年の歳月をかけて、欧米を中心に二十ヵ国以上の租税記録を過去数百 年にわたり分析、株式や債券や不動産などの資産を運用して得られる利益は、一般の人が働いて得られる所得の伸び(経済成長率)を常に上回っていることを証明した。つまり資産を持つ豊かな人はますます豊かになり、持たない人(よって自分で働いて稼ぐしかない人)との格差は広がるばかりということになる。
3 民主主義が機能不全を起こしている。
民主主義とは富を社会に再配分する仕組みである。最近は「トリクルダウン」という言葉を使うようだが、要するにたくさん儲けた人からたくさん税金を取って、それを貧しい人たちに配分しようという考え方である。これがうまくいかなくなっている。なぜなのか、考えてみましょう。
3 ピケティはどうしろと言っているのか
公正な競争の結果として生じる格差を、彼は否定していない。経済成長も重視する立場だ。私的財産の保護は、個人の自由や経済効率性を高める上で欠かせないとする。避けなければならないのは、財産が極端に特定の層に集中することだ。そのために世界規模で資産への累進的課税を強化すべきだと主張する。もちろん資産家たちは反対している。
為政者たちは? 極端な格差が持続的な経済成長や企業の発展にとって足かせになるという認識は、世界の政治、経済のリーダーたちに共有されているようだ。アメリカのオバマ大統領は、2014年の一般教書演説のなかで格差是正に言及していた。国際通貨基金や世界銀行の年次総会でも、所得格差と機会の不平等が議題になったという。
グローバル企業家たちは? ビル・ゲイツが世界最大の慈善基金団体を創設したり、マーク・ザッカーバーグが莫大な自己資産を社会貢献活動に寄付したり、ユニクロが難民を雇用したり、というように貧困や格差に無関心ではないようだ。しかし彼らは世界のもっとも富裕な1%の人たちだ。富の偏在が生じる仕組みそのものを変えようとしているわけではない。
4 これから世界はどうなっていくのだろう?
・グローバルな経済格差はどうなっていくと思いますか?
・世界各地でつづくテロや紛争はどうなっていくのでしょう。
・この世界のなかで、私たちはどのような生き方をすればいいのでしょう。
5 なぜ人は分かち合えないのか?
ここでは「ヒトラーとローマ教皇は兄弟」原理についてお話します。これは友人の森崎茂さんが考えた「内包的な親族」という概念にヒントを得て、ぼくがでっち上げたものです。こんなふうに世界をイメージすると、少し明るい気分になるのではないでしょうか。資料をお配りしますので、ぜひ感想を聞かせてください。できればレポートにして提出してください。
【宿題】
次回は人工知能(AI)について考えます。いま人工知能にはどんなことができるのでしょう。「シンギュラティ(技術的特異点)」という言葉について調べてきてください。できれば人工知能にかんする本を一冊読んでみてください。
【資料】 「ヒトラーとローマ教皇は兄弟」原理
ヒトラーは生まれながらにして、あのヒトラーだったわけではない。オーストリアのブラウナウに生まれ、ウィーンに出て国立芸術アカデミー美術学校の入学試験を受けるような(結果的に受験には失敗するのだが)、どこにでもいそうな画家志望の若者だった。意気消沈したアドルフは大都市ウィーンで孤独な生活を送ることになる。暮らしはそれほど貧しくはなかったようだ。すでに両親が亡くなっていたため孤児年金が支給されており、親の遺産からの収入もあった。風景画などを描いて訪れる観光客に売りつけるといった、お馴染みのアルバイトで日銭を稼いだりもしていたらしい。
これまた言うまでもないことだが、ローマ教皇も生まれたときからローマ教皇であったわけではない。ヒトラーにアロイスとクララという両親がいたように、未来のローマ教皇にも両親がいたわけで、さらにありえなくはない可能性として、可愛い妹もいたかもしれない。その妹は音楽家志望で、ピアニストかヴァイオリニストかオペラ歌手かなどは詳らかにしないが、とにかく音楽修業のためウィーンにやって来る……ということにして話を進めよう。
ヒトラーがウィーンに出てきたのは一九〇七年だ。そのころのウィーンといえば、皇帝フランツ・ヨーゼフによるハプスブルク朝が繁栄を誇った最後の時期、ジークムント・フロイト、アルノルト・シェーンベルク、エルンスト・マッハといった人々によって代表されるモダニズムの時代である。グスタフ・マーラーが若き日のブルーノ・ワルターを伴って定期的にウィトゲンシュタイン家の邸宅を訪れていたころ、エゴン・シーレやオスカー・ココシュカたちとウィーン分離派をはじめたクリムトが、金箔や強烈な色彩を用いた絢爛豪華なシャルロッテ・ヴォルターの肖像画を描いていたころ、ヒトラーもまた同じウィーンの街で平凡な風景画を描いていた。
そんな二人が出会う。挫折しかけた画家志望の青年とありきたりな音楽家志望の娘、つまりアドルフ・ヒトラーと未来のローマ教皇の妹が、第一次大戦前夜のウィーン、ワルツの流れる明るいカフェで恋に落ちる。誰だって、どんな二人だって恋に落ちる。ふとした偶然で、何気ないきっかけで、それまで見ず知らずだった二人が出会う。シチュエーションは無数に考えられる。ゲーテのウェルテルは、妹たちにパンを切ってやるシャルロッテの姿をドアの隙間から見た瞬間に恋に落ちる。ロベルト・ロッセリーニの『無防備都市』では、アパートの隣の部屋で鏡を掛けるための釘を打っている男に、未亡人であったアンナ・マニャーニが「うるさい!」と文句を言ったことから、二人は結婚の約束をかわす。いずれも死に至る恋である。ウェルテルは自殺してしまうし、ファシストに連行される結婚相手のあとを追ったアンナ・マニャーニは路上であっけなく射殺される。人を好きになれば、そういうことも起こる。どんなことだって起こりうる。
ヒトラーとローマ教皇の妹のあいだにも、いろんなことが起こりはじめる。二人がどのようにして出会ったかは、彼らだけの秘密にしておこう。出会ったことが重要なのだ。出会うはずのなかった二人が……そして恋に落ちる。恋する二人はウィーンのカフェでワルツを踊る。もちろん曲はヨハン・シュトラウス二世だ。「美しく青きドナウ」にあわせて踊るヒトラーとローマ教皇の妹を想像していただきたい。幸せな気分にならないだろうか?
もちろん二人も幸せだった。甘美な恍惚が二人を包む。まさにクリムトの絵のように。画家自身と恋人エミリーエ・フリーゲをモデルとした「接吻」を彼が描いたのは、一九〇七年から八年にかけてのことだ。そのころウィーンの明るいカフェでは、若い二人が揺れるシャンパン・グラスを片手に愛を誓い合っていた。青年は娘の耳元に囁きかける、「どんなことがあっても一緒になろうね」。ヴァイオリンの弓が刻む三拍子のリズムに乗って悪魔が出ていく。アドルフと呼ばれる青年のなかに、いまや邪悪なものはない。この娘を幸せにするということだけが、彼の頭を占めている。
それからさらに、いろんなことが二人のあいだで起こる。どんなことが起こったかというと、まあ、普通の男と女のあいだに起こるようなことだろう。野暮な詮索は抜きにして結論だけを言おう。結果的に、未来のヒトラーは生まれない。当然、ナチス・ドイツも誕生しない。第二次世界大戦もなければ、アウシュヴィッツやビルケナウといった地名が歴史に名をとどめることもない。
若きヒトラーが出会った娘は、さすがに未来のローマ教皇の妹だけあって、少し変わり者で偏狭なところもあった青年の心を薫育し、矯正し、心根の善い人間へと彼をつくり変えていく。強者は弱者に勝利するといった社会ダーウィニズム的な発想や、アーリア人種は他のどの人種よりも優秀だという奇怪な思い込み、ユダヤ人にたいする常軌を逸した嫌悪や憎しみ、詰まるところ『我が闘争』に読まれるようなグロテスクな考え方は、ヒトラーのなかから一掃される。ユダヤ人のことを寄生虫だの病原菌だのと口汚く罵るアドルフは、愛する女性の前で影をひそめる。とりわけ血の純潔などという浅薄な発想は、どこを探しても彼のなかには見つからない。人種も民族も異なる男女が明るいウィーンのカフェで愛を誓い合うことで、そんなものは易々と超えられることを彼自身が身をもって体験したからだ。こうして世界中の人たちが知っているヒトラーは未遂に終わる。